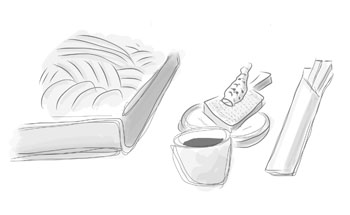蕎麦の刺身
シアトルから日本へ帰国したときの話。
語学留学で滞在していたシアトルから日本へ戻り、さてさて仕事を探さねばと就職情報誌を眺めていた。テレビから聞こえてくる日本語にまだ違和感があるころのこと。頭の中で駆け巡っていたのは楽しかった想い出。あの街でまた暮らしたい。アメリカでの仕事はないものかとページをめくった。
そのとき、ある求人が目に留まった。なにやら東京の老舗手打ち蕎麦屋がニューヨークへ出店を予定しているという。手打ち蕎麦どころか料理など全く知らない世界だったが、なにか惹かれるものがあったのでとりあえず連絡してみることにした。
数日後、面接を受けに行くため東京のとある住宅街を歩いた。澄んだ秋の空の下、瓦屋根の家々を抜ける道がどことなく狭く感じられる。生活の息遣いが肌に触れそうな距離に感じられる日本が懐かしい。
「ガラガラ…」格子戸を開け蕎麦屋に入る。途端ダシのいい香りに包まれる。ガラス張りのブースの中では職人さんが蕎麦を打つ。「ピシンッ、ピシンッ」湖面を走る漣のような正確なリズムが静寂に響く。
そして社長さんとの面接が始まった。並々ならぬ情熱を持つ社長さんは饒舌に蕎麦を語る。「まあ、蕎麦でも食っていけ」途中せいろに盛られた蕎麦を出された。「蕎麦というのはつゆだけで食べるのがいちばんシンプルで旨いんだ」と目を細める。緊張しながら、でも遠慮なくいただいてみた。まず驚いたのはその歯応え。麺の中で蕎麦の粒々がプリプリとしている。噛むたびに蕎麦の強い香りが広がる。「これが本物の蕎麦…」その衝撃は今でも記憶の奥で波を打つ。
毎朝石臼で挽かれる蕎麦粉は粗くザラザラで粉というより「砕かれた実の粒々」。まるで砂のような蕎麦粉を職人は高い技術でこね、そして打つ。その挽きたて、打ちたて、茹でたてのいわゆる「三たて」の蕎麦の歯応えと香りには、ひと口ごと鮮やかな出逢いがある。数年後、お店へ食べに来てくれた友人がこう語った。噛むごとに口の中で弾けるその鮮やかさはまるで「蕎麦の刺身」のようだと。
かくしてこの蕎麦屋で働き始めた。そして3年後にニューヨーク支店が開店し、それとともに渡米。Sobaはニューヨーク・タイムズの三ツ星をはじめ高い評価を得ることとなった。ぼくは自分の夢を追うため渡米5年後に退職。その後パリへ渡るなどいろいろな料理を経験し、それから、ずいぶんと年月も過ぎた。
現在は「食と健康」について考える仕事をしている。そして今でも注文があれば蕎麦を打つ。最高の蕎麦の実や道具を揃えているわけではないが、あの蕎麦の刺身に近づくよう精魂込めて打つ。ゆっくりとかえしを熟成させ、独自の配合の出汁をとり、蕎麦の実を挽き、そして、ピシンッ、ピシンッと麺棒を走らせる。

浅沼(Jay)秀二
シェフ、ホリスティック・ヘルス・コーチ。蕎麦、フレンチ、懐石、インド料理などの経験を活かし、「食と健康の未来」を追求しながら、「食と人との繋がり」を探し求める。オーガニック納豆、麹食品など健康食品も取り扱っている。セミナー、講演の依頼も受け付け中。
ブログ:www.ameblo.jp/nattoya
メール:nattoya@gmail.com