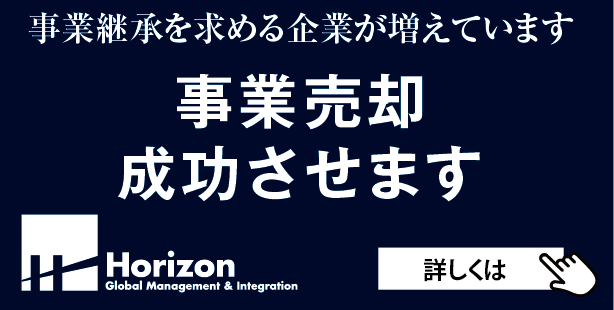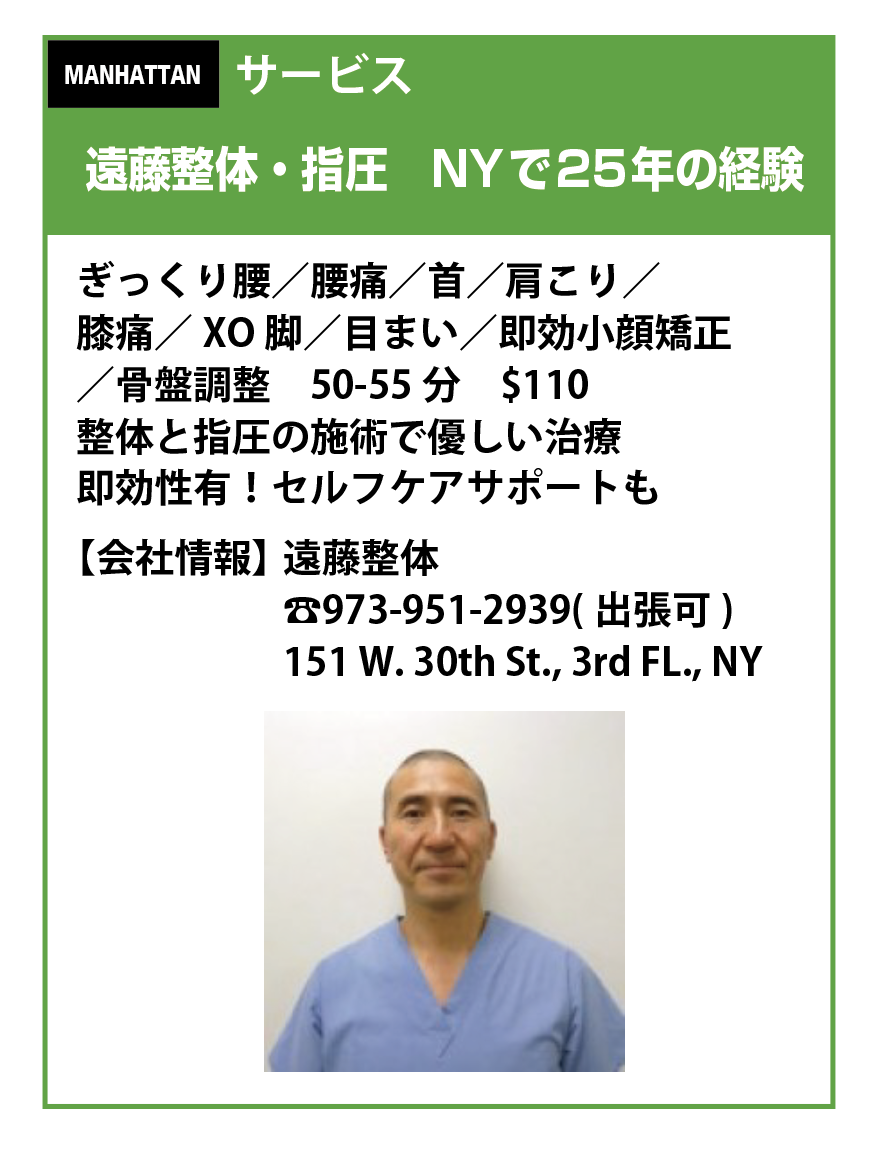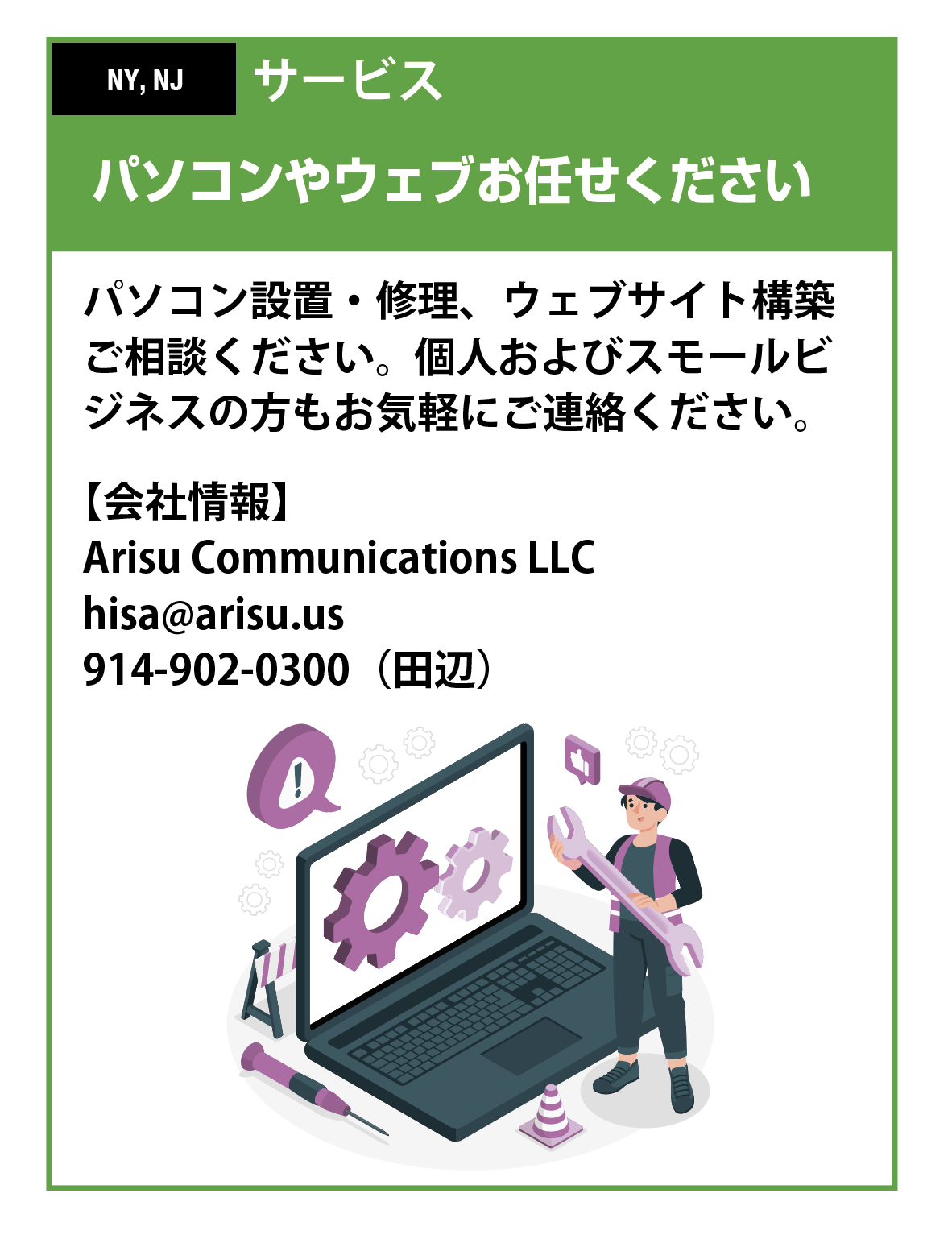連載697 地球温暖化の不都合な真実(1) 長期的に見れば「氷期」に向かっているのか? (下)
縄文時代、東京や横浜は海のなかだった
では、ここでよく考えてみてほしい。
現在、最大の課題とされる地球温暖化は、たった150年ほどの話なのである。しかもまだ気温はそこまで上昇していない。
そこで、目を転じて、もっと長い目で歴史を見れば、前記したバイキングが活躍した「中世温暖期」もあるし、さらにもっと長い目で見ると、たとえば日本の縄文時代前期(約6500~6000年前)のころの世界は、いまより気温が2度は高かった。そのため、海水面はいまより4~6メートルも高かった(地質学的に「完新世海進」と呼ばれる)。東京も、私が住む横浜も海の中だったのだ。
温暖化が叫ばれてから、必ず取り上げられるのが、北極と南極の氷が溶解して海水面が上昇するという話だ。しかし、それは、6500~6000年前に、世界が戻るだけという話にすぎない。
シロクマ絶滅とツバルの水没のマヤカシ
北極の場合、氷が溶ければシロクマが絶滅するという。そのため、かわいそうなシロクマの映像が、繰り返し流されてきた。しかし、完新世海進の時期には、北極に氷はなかった。シロクマは流氷がないと餌が取れないと言われるが、それなら、シロクマはとっくに絶滅していたはずだ。
海水面の上昇で必ず取り上げられるのが、南太平洋の島国ツバルである。ツバルの海水面はIPCCによると、年平均3.9ミリ上昇しているとされ、このままでいくと 2100年には人が住めなくなると言われている。
しかし、2018年にニュージーランドのオークランド大学の研究チームが、科学誌『ネイチャー・コミュニケーションズ』に発表した論文によると、ツバルを形成する9つの環礁のうち8つでは面積が広がっていて、ツバルの総面積は73.5ヘクタール(2.9%)増えたというのだ。
サンゴ礁の島々では、年々サンゴが成長して環礁が高くなり、そこに砂が堆積して島が拡大していくのだという。
溶解して海水面が上昇するという話だ。しかし、それは、6500~6000年前に、世界が戻るだけという話にすぎない。
「氷期」と「間氷期」が周期的に繰り返す
地球の歴史は、「氷期」(glacial period)と「間氷期」( interglacial period)の繰り返しである。寒くなったり暖かくなったりの繰り返しは、地球誕生以来続いている。そのサイクルは大きくは何千万年、何億年単位だが、もっと短い時間軸で見ると10万年周期である。その度に海水面の高さは、100メートル以上も変動してきた。
さらに、この10万年の間にも、数百年のサイクルでミニ氷期(寒冷期)とミニ間氷期(温暖期)繰り返されてきた。
セルビアの地球物理学者M・ミランコビッチは、過去260万年間に氷期と間氷期が交互にやって来ている原因を、太陽の放射熱量の変化に求めた。北半球の高緯度地域の夏季日射量が減少すると氷期になり、日射量が増加すると間氷期になることを、研究により指摘した。その結果、このことを「ミラコビッチ・サイクル」( Milankovitch’s cycle)と呼んでいる。
そしていまは、最終氷期が終わった間氷期で、そのなかで寒冷期と温暖期が周期的に繰り返されている。現在の地球温暖化はそのようなサイクルが原因であり、いずれ、氷期がやって来るという。したがって、現在騒がれている温暖化など取るに足りない問題だという見方があるのだ。
地球温暖化が科学に基づかない仕組まれた陰謀だとする陰謀論もある。このような陰謀論も影響しているのか、地球温暖化に懐疑的な日本人は、欧米諸国に比べるとかなり多い。
じつは、私もそうした見方に傾いていたことがあり、いまも温暖化には懐疑的だ。
(つづく)
この続きは2月3日(木)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで