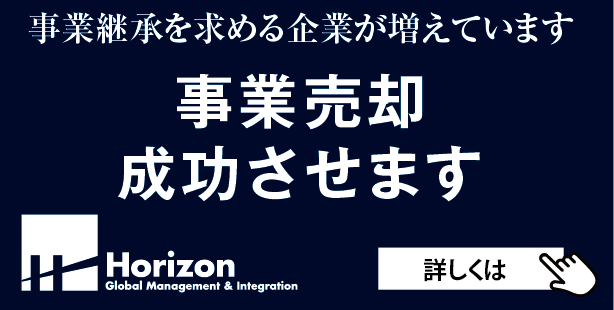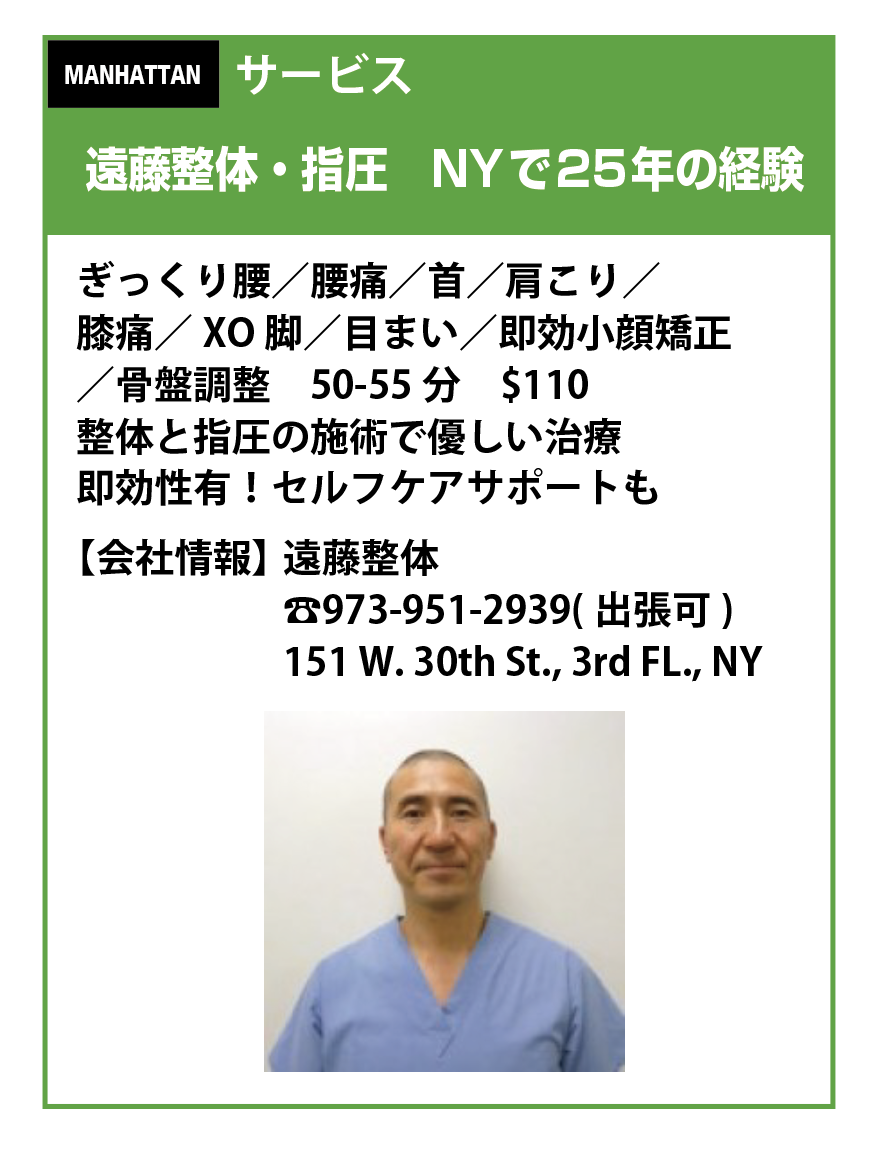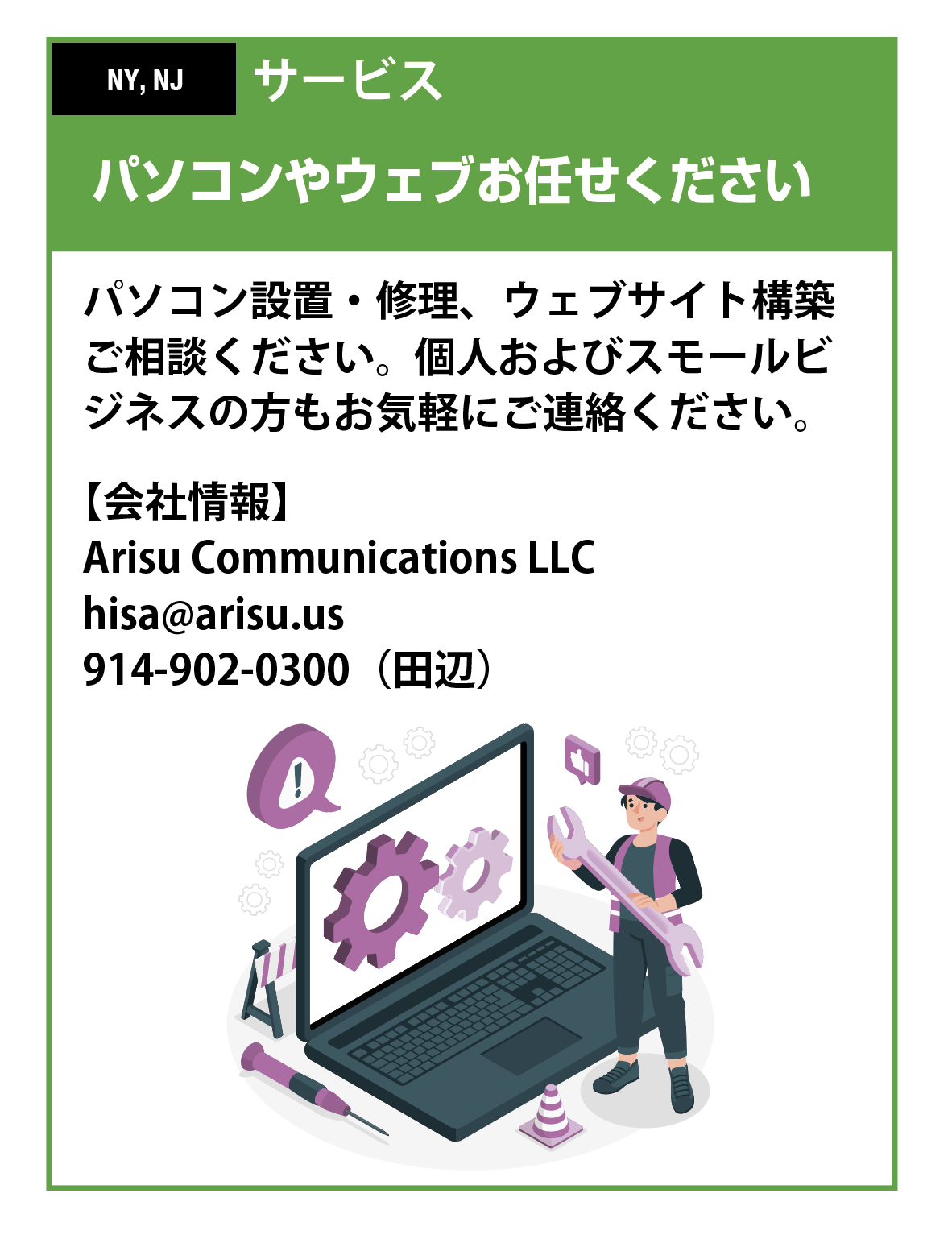連載728 台湾有事、米中戦争にリアリティはない
アメリカも中国もそこまで愚かではない(中2)
(この記事の初出は2月15日)
なぜ、アメリカは中国を敵視するのか?
ここで、考えてほしいのは、なぜアメリカは中国を敵視するようになったかである。
一般的に言われているのは、アメリカは中国を世界経済に組み入れば、やがて民主化すると考えてきた。いずれ、資本主義自由経済に転換していかざるをえないだろうとしてきた。しかし、中国は異質の存在であり続けた。アメリカがつくったIT経済、ネット経済は、じつは強権国家と相性がよく、国民を簡単に支配できたからだ。
アメリカが中国を許せない点を具体的に見ると、(1)人権を無視し、民族浄化をしているから許せない(2)先端技術、ハイテク分野で負けそうなので許せない(3)非白人国家がこれ以上力を持つことが許せない——などが挙げられる。
そして、その背景には、このままいくと、2030年代にGDPで中国に逆転される予想が現実味を帯びてきたということもあるだろう。
つまり、アメリカは、中国に世界覇権を奪われることだけは、阻止したいのである。
覇権戦争では当時国は勝者にならない
アメリカは民主主義国家で、共和制政体だが、政権中枢部は常に自国をローマ帝国になぞらえている。ローマ帝国の盛衰史は、アメリカの政治家にとっての必須の教養である。中国は、そんなアメリカ帝国の覇権に対する挑戦者だから、必ず退けなければならない。
これは、アメリカの政治家なら、リベラル、保守にかかわらず誰もが持つ共通認識である。
覇権国と覇権挑戦国の間で覇権をめぐる戦争が起こった場合、歴史を見ると、勝ち残った国が次の覇権国になるとは限らない。覇権戦争では、当時国は勝者にならないのだ。多くの場合、その争いの外にいた別の国が次の覇権を握っている。
ここから得られる教訓は、覇権は戦争で奪えないということだ。台湾をめぐって実際に戦争をするなど、そんな愚かなことを、アメリカは望んでいない。おそらく中国も望んでいないだろう。
米軍トップが中国に攻撃しないと電話
トランプ前大統領、バイデン大統領の台湾をめぐる強いメッセージの裏で、実際はなにが起こっていたのか、それが昨年の9月に暴露された。
ワシントン・ポスト紙のボブ・ウッドワード、ロバート・コスタ両記者による著書『Peril』のなかで、トランプ政権時(トランプ支持者による連邦議会占拠事件が起こった2021年1月6日の2日後)に、アメリカ軍トップのマーク・ミリー統合参謀本部議長が、中国人民解放軍のトップに電話をかけ、中国を攻撃する意図はないと説明していた事実が明かされたのだ。
「これは越権行為に当たる」「反逆罪だ」と、当時、保守派は激しく非難した。しかし、ホワイトハウスは、ミリー氏を全面的に擁護したのである。
本では、ミリー統合参謀本部議長が中国軍将官に電話をしたのは、中国を安心させるためだったことが詳述されていた。また、トランプ大統領による危険な軍事攻撃の命令の可能性を制限しようと試みたとも書かれていた。
これが本当なら、アメリカ軍は中国と戦火を交える気はないのだ。
その後、ミリー統合参謀本部議長は、中国が台湾を侵攻する可能性は当面は低いという認識を示し続けている。
昨年11月に行われたシンクタンクのアスペン研究所のフォーラムでは、「中国は近い将来、台湾へ行動を起こそうと準備しているか」と問われ、「私の分析によれば半年や1、2年という近い将来に起こり得えるとは思わない」と否定した。
(つづく)
この続きは3月21日(月)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。 ※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
→ 最新のニュース一覧はこちら←
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで