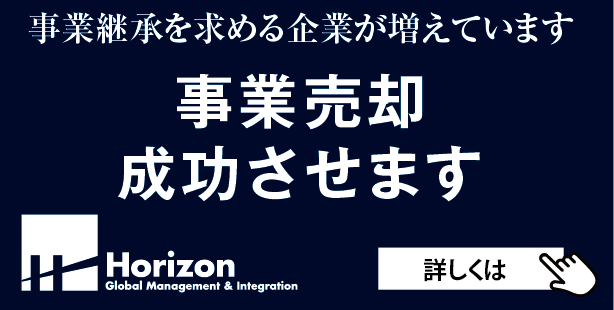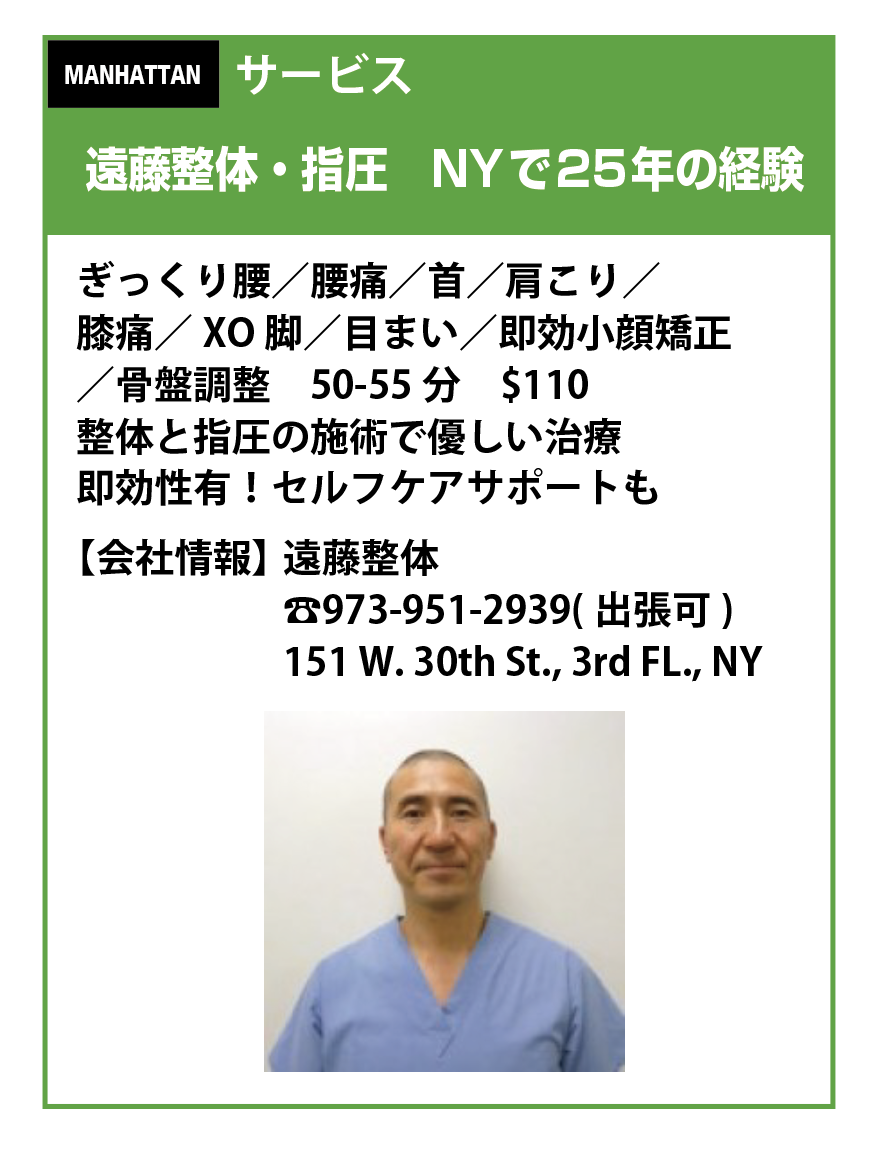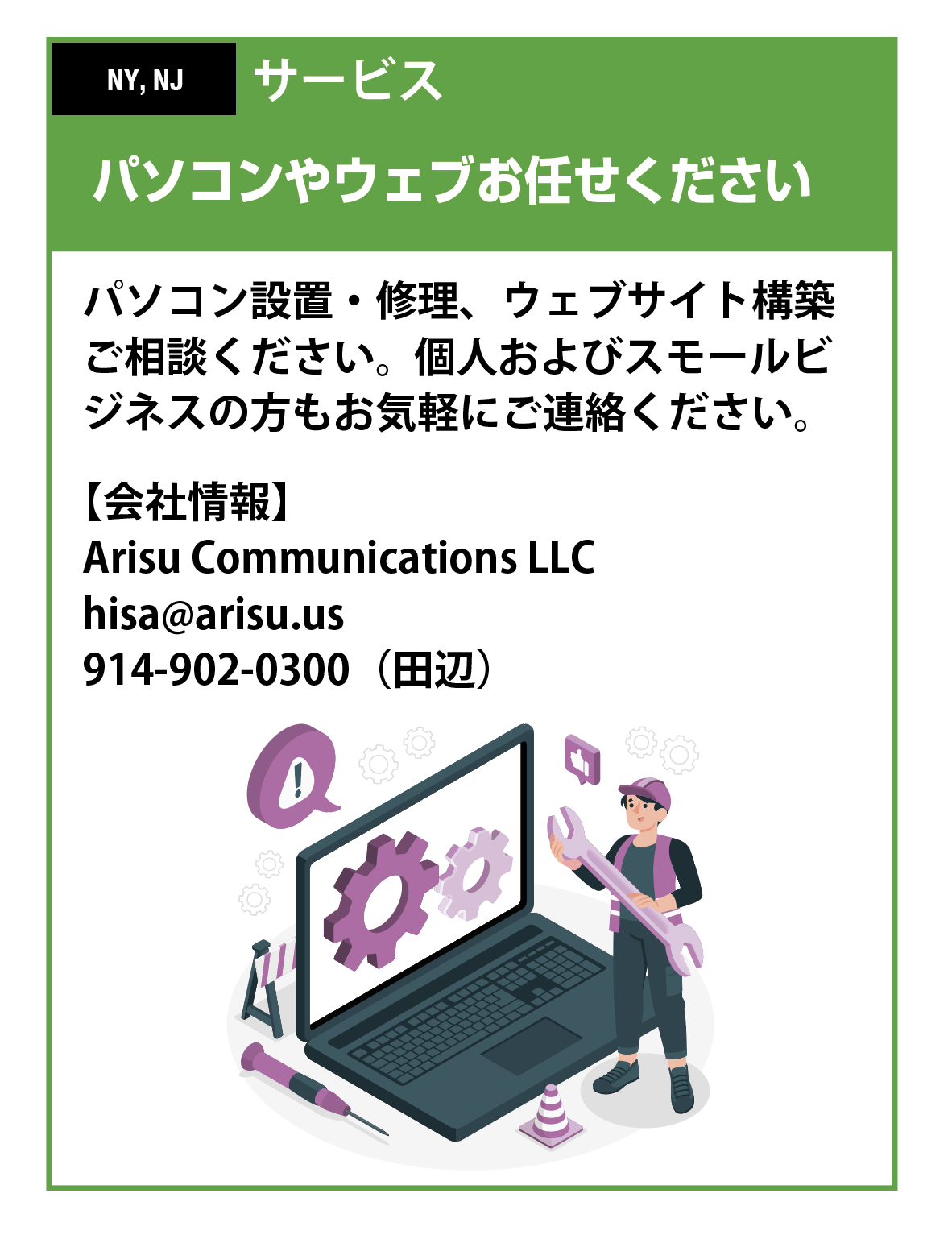連載818 デジタル庁ができてもデジタル化できず。
「デジタル後進国」はいつまで続く (完)
(この記事の初出は6月21日)
IT人材を養成しようとしない日本の組織
デジタル化推進のためにデジタル庁をつくると言うことなら、誰でも言える。しかし、実際にやるとなると、それをになう人材がいないから、ベンダーに丸投げすることになる。そして、そのベンダーにいるIT技術者は、システムづくりがわからない担当者と仕事をして、日々疲弊していく。
アマゾンはビッグテックの1社に数えられるが、実際にはデジタルとは関係ない仕事も多い。しかし、倉庫のワーカーにいたるまで約10万人の社員全員に、デジタル能力トレーニングを実施している。アマゾン全体では1年間に約1億ドルの予算を、社員のデジタル教育に使っている。
システム開発のコストは、そのほとんどを人件費が占める。したがって、チームの人間のなかにデジタルがわからない人間がいると時間がかかり、その分、費用が上乗せされていく。わからない人材というのはほとんどが発注側の人間であるのは言うまでない。
このことは、さらなるコストを招く。発注側は納品されたシステムの中身を評価することができないからだ。
また、不備があった場合、運用中にトラブルが発生した場合は、またもやベンダーに丸投げされる。こうして、限りない「負の連鎖」のなかで、日本のデジタル化は行われている。
生体認証システムをゼロから構築せよ!
日本の公官庁や企業は、ほとんどが「縦割り社会」である。この縦割りのなかでベンダー丸投げのデジタル化が行われると、箇々別々の独自システムができあがる。
したがって、それを運用するにも、改修するにも、開発したベンダー以外にはできない。もし乗り換えるとしたら、それはまたゼロからやり直すことになり、多大なコストがかかる。
こうして日本では、12省庁、47都道府県、1718市町村などが、それぞれバラバラにシステムを開発したため、結局は、全体では機能しなくなってしまった。マイナンバーがその典型で、住基ネットからスタートした時点で、ベンダーが自治体ごとに異なっている。
最初に生体認証を持った国民データベースをつくるべきだったのに、誰もそんなことを提唱しなかった。
結局、このままデジタル庁が進んでいけば、この問題に直面する。「デジタル田園都市構想」などと言って、高齢者にスマホの使い方を教えても、それでデジタル化ができるわけではない。
求められるのは、国民全員が使えるシステムを、ゼロから構築することだ。そのシステムは、スマホと生体認証を前提とし、いずれはマイナンバーなどのカードを持ち歩かなくても済むようにすることだ。はたして、デジタル庁にそれができるのか? 私たちは、ただただ見ているだけしかないのだ。
(了)
【読者のみなさまへ】本コラムに対する問い合わせ、ご意見、ご要望は、
私のメールアドレスまでお寄せください→ junpay0801@gmail.com

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
→ 最新のニュース一覧はこちら←
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで