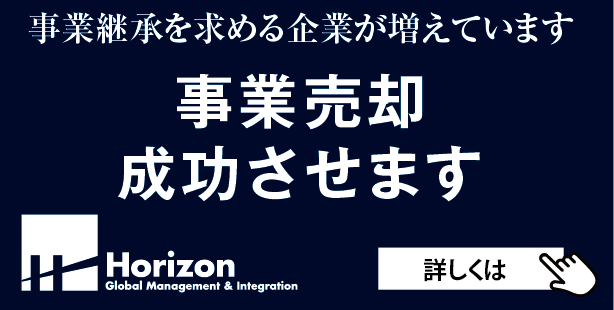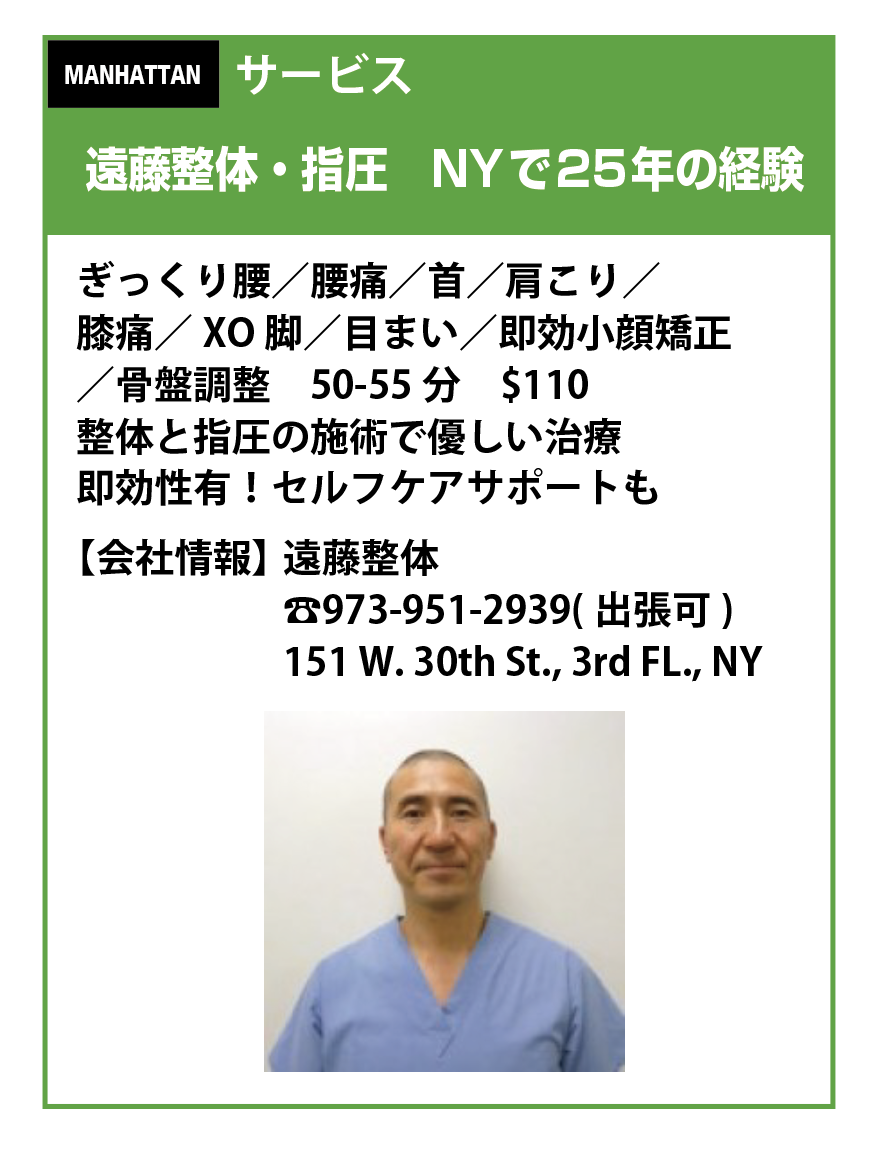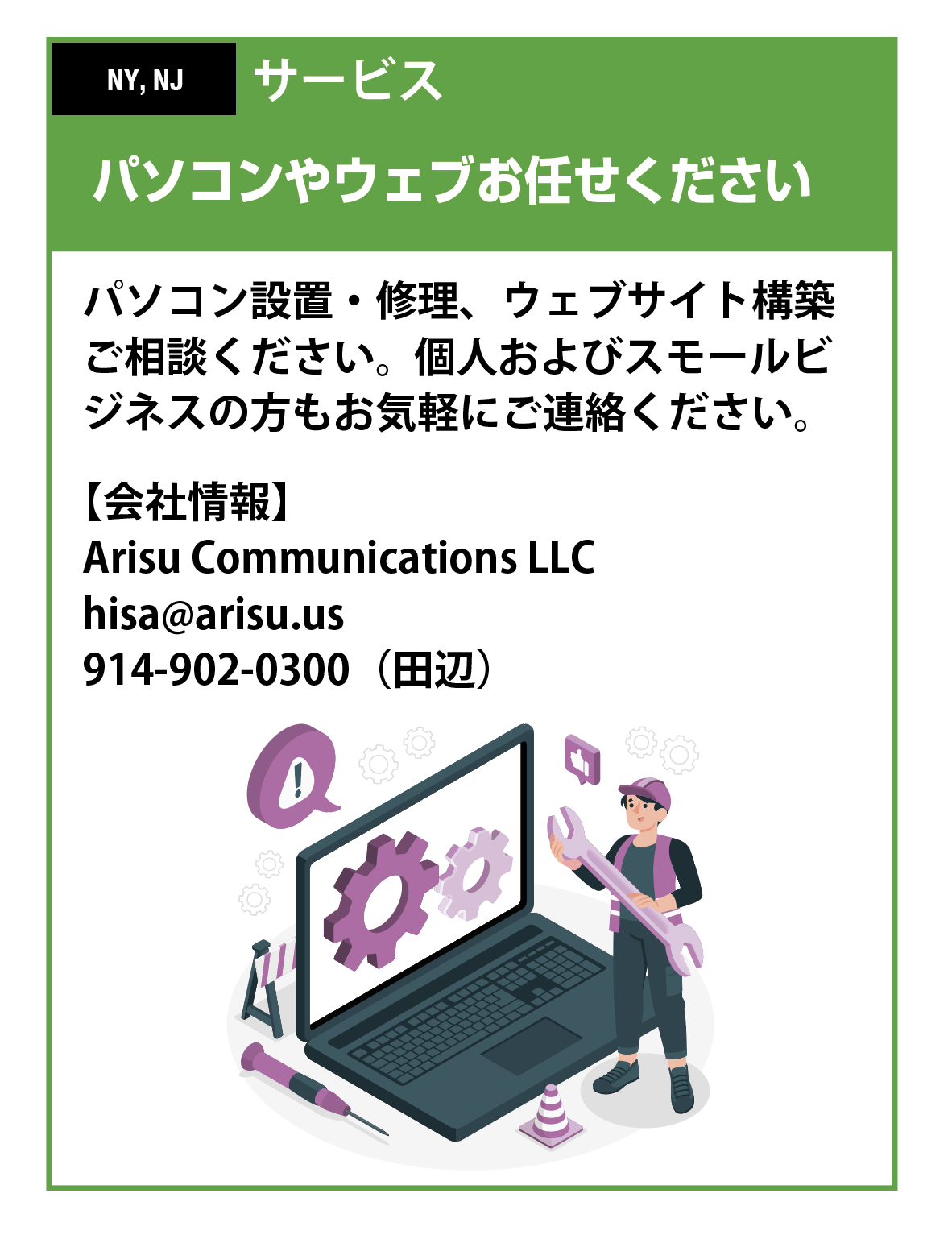連載874 先進国から転落中の日本の「辺境、あるある」
(上)
(この記事の初出は9月20日)
いよいよ、1週間後の9月27日に、安倍元総理の「国葬」が行われる。批判続出のなかで強行されるこの葬儀は、日本の凋落を象徴するイベントになるのは間違いない。
なにより、エリザベス女王の葬儀と比べられ、そのみすぼらしさが世界に知れ渡る。
いったいなぜ、日本はここまで凋落してしまったのだろうか。日本はいま「先進国から転落中」というより、世界の「辺境国家」「ガラパゴス国家」になってしまっている。
そこで今回は、日本の「辺境、あるある」をまとめて取り上げてみたい。
日本の玄関、成田空港は「辺境空港」か?
なんといっても、日本の辺境ぶりを感じるのは、成田空港である。これほどみすぼらしい国際空港は、世界の主要国の首都にはない。毎回、成田を利用するたびに思うのは、ここが日本の玄関だろうか、どこか辺境の国のローカル空港ではないかということだ。
たとえば、シカゴのオヘア空港、ロンドンのヒースロー空港、ヘルシンキのバンダー空港、アジアではシンガポールのチャンギ空港、バンコクのスワンナプーム空港、北京の首都国際空港、香港の香港国際空港などから成田に戻ったとき、本当にがっかりする。
香港からの最終便は、だいたい夜9時前後に成田に着く。通関して第2ターミナル到着ロビーに出ると、レストランなどの店はほとんど閉まり、辺りは閑散としている。そのせいか、施設の老朽ぶりが目立つ。
成田の場合、午後10時ごろから朝方まで、一部のコンビニを除いてほぼすべての店舗が閉まる。24時間営業の店舗は、飲食店では第2ターミナルの吉野屋1軒だけだ。
これは、世界の主要空港では考えられないことだ。シンガポールのチャンギ空港を例にとれば、レストランやスーパーは深夜の時間帯は閉まるが、フードコートは営業しており、ほかの多くの施設も営業している。ラウンジ、シャワールームはもとより、映画館、室内庭園まで営業している。
成田空港の難点は、都心までのアクセスの悪さだ。電車にしてもバス、タクシーにしても1時間以上かかるというのは、首都の空港としてはありえない。
さらに、国内線が少なく、乗り継ぎの便がよくない。これは長いこと、「国際線は成田、国内線は羽田」としてきた航空行政のツケだ。オープンスカイとハブ化が進んだいま、こんなことをやっている国はない。
それに気がつき、羽田を拡充してきたが、まだ世界の趨勢に追いついてない。
「コロナ鎖国」で「ジャパン・パッシング」
成田空港の辺境ぶりで思うのは、これまでの政府の「コロナ鎖国」の頑迷ぶりだ。なにがなんでも海外からの感染者の入国を防ごうと始めた「水際対策」をいまなお続けている。これには、本当に呆れる。これで、日本は完全なガラパゴスになってしまった。
9月7日になってようやく制限が一部緩和されたが、個人旅行は認めず、ビザ取得義務は継続中だ。
この「コロナ鎖国」により成田でなにが起こったかというと、「成田素通り」=「ジャパン・パッシング」である。「コロナ鎖国」で閑散としている成田で、常にごった返しているところがある。トランジットカウンターだ。
JALやANAの北米路線がアメリカから成田に着くと、日本人よりはるかに多くの東南アジアの旅行客が降りて来る。彼らは、成田で乗り換え、マニラやバンコクなどに向かう。
この反対も同じだ。東南アジアの各都市から成田でトランジットとして北米に向かうのだ。
コロナ禍になって、インバウンドはほぼ消滅した。しかし、ジャパン・パッシングは大盛況である。これは、中国、香港が厳しいコロナ対策を継続してきたせいでもある。そのため、香港発、中国発の北米路線はほとんど飛んでいない。したがって、東南アジア各国の北米トラベラーは、成田か韓国の仁川に集中するようになったのだ。
本当にいつまで、こんな鎖国政策をやっているのだろうか。いまや日本のほうが海外より感染者数が圧倒的に多い。いまだに国内で「マスク強制」をしている国がやるようなことではないし、科学的根拠もまったくない。
(つづく)
この続きは10月19日(水)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで