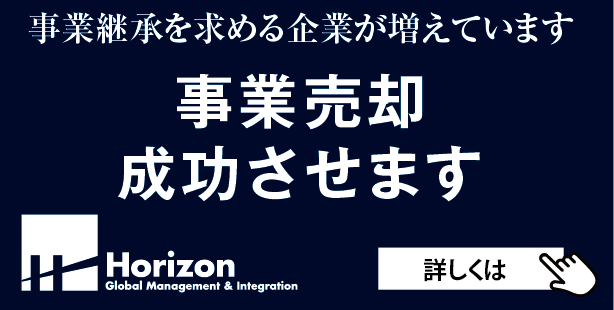連載917 防衛費増強が虚しくなる
自衛隊の絶望的な「ドローン」立ち遅れ(中)
(この記事の初出は2022年11月22日)
巨額の建造費、訓練された乗組員は無意味
ウクライナが使った自爆型水上ドローンは、当初、アメリカが提供したものと言われた。すでに4月の段階で、アメリカ国防総省のジョン・カービー報道官は、水上ドローンをウクライナに提供することを明らかにしていたからだ。
アメリカ軍は、水上ドローンの重要性を早くから認識し、実戦配備を行なってきた。たとえばペルシャ湾では、イラン包囲網として大量の水上ドローンを配備しようとしている。
ところが、セバストポリ攻撃からしばらくして、ロシア国防省は、英国をウクライナに水上ドローンを提供したと非難した。これを受けて、英国も一定数の水上ドローンをウクライナに供与し、セバストポリのロシア黒海艦隊の艦艇に対する攻撃に関与したと発表した。
いずれにしても、こうした水上ドローンや水中ドローンが、海の戦いを大きく変えていくことは確かだ。莫大な建造費をかけてつくられた軍艦と訓練された乗組員が、低価格で無人のドローンの波状攻撃によって、簡単に破壊・駆逐されてしまうのである。
こうなると、大艦隊を編成して制海権を握ってみたり、それによって敵国を威嚇してみたりすることはできなくなる。いまや艦隊の要となった空母もドローンによって無力化される可能性が出てきた。
安価で人命を尊重できるという2大利点
セバストポリでは海戦におけるドローンの有効性が証明されたが、空のドローンに関しては、すでに多くの有効実例がある。
アメリカ軍によって、ドローンが本格的に使われたのは、2001年のアフガン戦争が最初だ。このとき、アメリカは、人命とコストを考慮して、タリバン勢力をドローンによって攻撃した。ただ、当時はまだドローンの性能が低く、民間人を殺傷してしまう誤爆も多発した。
とはいえ、ドローンは安価でコストパフォーマンスが高い。しかも、無人兵器だから人命を尊重できる。この2つの利点から、その後、ドローンは世界中で使われるようになった。
アメリカや中国のような軍事大国ばかりか、新興国でも開発・実戦配備が進んだ。たとえば、中国の安価な民生用ドローンを軍事用に転用する動きも広がった。また、部品さえ調達できれば、モジュール生産で軍事用ドローンは簡単につくれる。
もはやドローンによる攻撃は当たり前に
今回のウクライナ戦争でも、秋葉原でフツーに売られている日本メーカーの模型飛行機用エンジンを使って、ウクライナは軍事用ドローンをつくった。それを偵察用に使い、ロシア軍の動きをいち早く察知して、首都キーフの攻略を防いだ。また、ウクライナ軍は、攻撃型ドローンも積極的に投入した。
それは、これまでにドローンが有効だという前例が積み上がってきたからだ。
たとえば、2020年まで内戦が続いてきたリビアでは、ドローンは日常的に使われてきた。リビア国民軍と反政府武装勢力は、それぞれトルコ、中国からドローンを調達して、戦場に投入し、イーブンの戦いを繰り広げた。
またリビアでは、AIを搭載し、人間の判断を介さずに自律的に敵を攻撃する「キラーロボット」(自律型殺傷兵器:LAWS)も登場した。
2019年、イエメンでは、反体制派フーシがイエメン政府を支援する隣国サウジアラビアの最大の石油企業サウジアラムコの施設を自爆型ドローンで攻撃した。この攻撃は大成功し、サウジアラビアの石油生産量は一時半減した。
(つづく)
この続きは1月6日(金)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

春の満月「ピンクムーン」がNYの夜空を幻想的に、 日時やおすすめ鑑賞スポットは?
-

なぜ? アメリカの観光客が減少傾向に「30〜60%も…」、NY観光業で深まる懸念
-

アメリカのスーパーの食材に「危険なレベル」の残留農薬、気をつけるべき野菜や果物は?
-

生ごみのコンポスト義務化、守られず ごみ分別違反に4月1日から罰金
-

トレジョの人気すぎるミニトートに新色、各店舗からは「買えた」「買えなかった」の声 ebayではすでに約16倍の価格で転売!?
-

NYで「ソメイヨシノ」が見られる、お花見スポット5選 桜のトンネルや隠れた名所も
-

北米初のユニクロ「カフェ」がNYにオープン、気になるメニューや価格は?
-

物件高騰が続くNY、今が “買い時” な街とは? 「家を買うのにオススメなエリア」トップ10が発表
-

NY・ソーホーで白昼に起きた悲劇、ホームレスにガラスで首を刺され…女性が重体
-

NYのクイーンズに巨大な「エンタメ施設」が誕生、フードホールにライブ会場も 総工費は約80億ドル