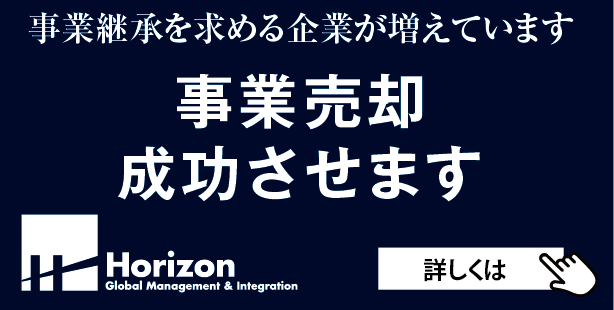連載926 防衛費増額だけでは日本は守れない。
なぜ、日本の防衛はここまでダメになったのか?(中1)
(この記事の初出は2022年12月13日)
抑止力としての核保有まで踏み込むべき
国会もメディアも、与党も野党も、右派も左派も、そして専門家までもが、こんな無意味な議論をしなければならないのは、これまで政府がミサイル配備は専守防衛に基づく「迎撃」のみという虚構を言い続けてきたからだ。このナンセンスな理屈に縛られるのを止めない限り、本当の国防議論はできない。
日本がいま必要なのは、アメリカの核の傘だけでは担保されなくなった安全保障をどうやって担保するかだ。すでに、現代の戦争は過去の戦争と大きく変わっている。サイバー空間、宇宙空間も戦争領域であり、極超音速ミサイルやドローン、そしてAIの活用など、武力そのものも大きく変化している。
そんななかで、やはり核だけは、いまも十分な抑止力を持っていると考えられている。
となると、ロシアも中国も、そして北朝鮮も核兵器保有国だから、そうした国々に対して抑止力を持つには、それ相応の「攻撃能力」(報復力と置き換えていい)がいるということだ。おそらく、それは、敵基地や軍事拠点、そして敵都市をも破壊できる力である。
もっと踏み込めば、こちらも核武装をすることである。「相互確証破壊」を成立させるためには、この選択肢以外にない。つまり、最終的な選択肢として核武装もあるという前提、現実論に立って議論を進めないと、国民の生命と安全は守れない。
反撃できる長射程ミサイルの導入・整備
では、防衛費を増額して、政府はいったいなにをしようとしているのか? そして、いわゆる反撃能力とは、具体的になにを指すのだろうか?
まず挙げられているのは、長射程ミサイルの導入・整備である。その候補として、アメリカから巡航ミサイルの「トマホーク」(射程1250キロ以上)を500発購入し、さらに国産ミサイルの改良や開発を進めるという。とりあえずは、トマホーク により当面の反撃能力を確保し、いずれ国産ミサイルの改良と開発によって能力の向上を目指すというのだ。
しかし、トマホークは、30年も前の湾岸戦争で効果を発揮したミサイルであり、その後の兵器の進化の歴史に追いついていない。その点を考えると、トマホークは防空システムが機能しない防衛後進国で有効な兵器であり、アメリカはすでに旧型兵器として廃棄しようとしているのだ。
それに敵基地攻撃をするには、ミサイルより、細かな回避軌道がとれ、ステルス性がある無人攻撃型ドローンがもっとも有効で、イランやトルコでさえ、こうしたドローンを自国開発している。
つまり、この点において、現在の日本の反撃能力保持の方向性は、どこか大きくずれている。では、トマホークに続く国産ミサイルというのはなにか?
国産の「スタンドオフ・ミサイル」を配備
現在、陸上自衛隊は、「12式地対艦誘導弾」という三菱重工が開発・製造した地対艦ミサイルを実戦配備している。2012年度から調達が開始されたもので、中国海軍との戦闘状態になることを想定して、南西地域の防衛体制を強化するため、宮古島、石垣島のほか、鹿児島県の奄美大島、熊本市に配備されている。
「12式地対艦誘導弾」は俗に「ひと・に式」と呼ばれ、その射程は百数十キロ。これを改良して射程を伸ばし、敵基地がある中国本土、朝鮮半島に届くようにしようというのだ。つまり、日本独自の「スタンドオフ・ミサイル」(長射程巡航ミサイル)を保持しようというのである。
防衛省は、「ひと・に」改良型スタンドオフ・ミサイルを10パターン以上同時開発し、地上、艦艇、航空機からそれぞれ発射できるようにする計画という。
改良がうまくいけば、射程1000キロ以上の地上発射型は早くて2026年度から配備し、さらにマッハ5以上の極超音速誘導ミサイルも開発して、こちらは2028年度以降の装備化を目指すという。
また、潜水艦発射型ミサイルも計画されているというから、まさにスタンドオフ・ミサイルのオンパレードである。これらのミサイル開発・装備には5兆円が投じられるという。
(つづく)
この続きは1月20日(金)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

春の満月「ピンクムーン」がNYの夜空を幻想的に、 日時やおすすめ鑑賞スポットは?
-

なぜ? アメリカの観光客が減少傾向に「30〜60%も…」、NY観光業で深まる懸念
-

アメリカのスーパーの食材に「危険なレベル」の残留農薬、気をつけるべき野菜や果物は?
-

生ごみのコンポスト義務化、守られず ごみ分別違反に4月1日から罰金
-

トレジョの人気すぎるミニトートに新色、各店舗からは「買えた」「買えなかった」の声 ebayではすでに約16倍の価格で転売!?
-

NYで「ソメイヨシノ」が見られる、お花見スポット5選 桜のトンネルや隠れた名所も
-

北米初のユニクロ「カフェ」がNYにオープン、気になるメニューや価格は?
-

物件高騰が続くNY、今が “買い時” な街とは? 「家を買うのにオススメなエリア」トップ10が発表
-

NY・ソーホーで白昼に起きた悲劇、ホームレスにガラスで首を刺され…女性が重体
-

NYのクイーンズに巨大な「エンタメ施設」が誕生、フードホールにライブ会場も 総工費は約80億ドル