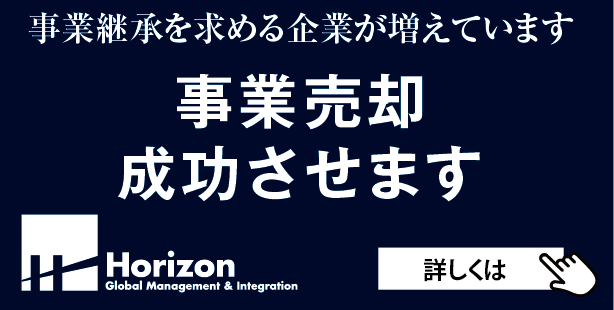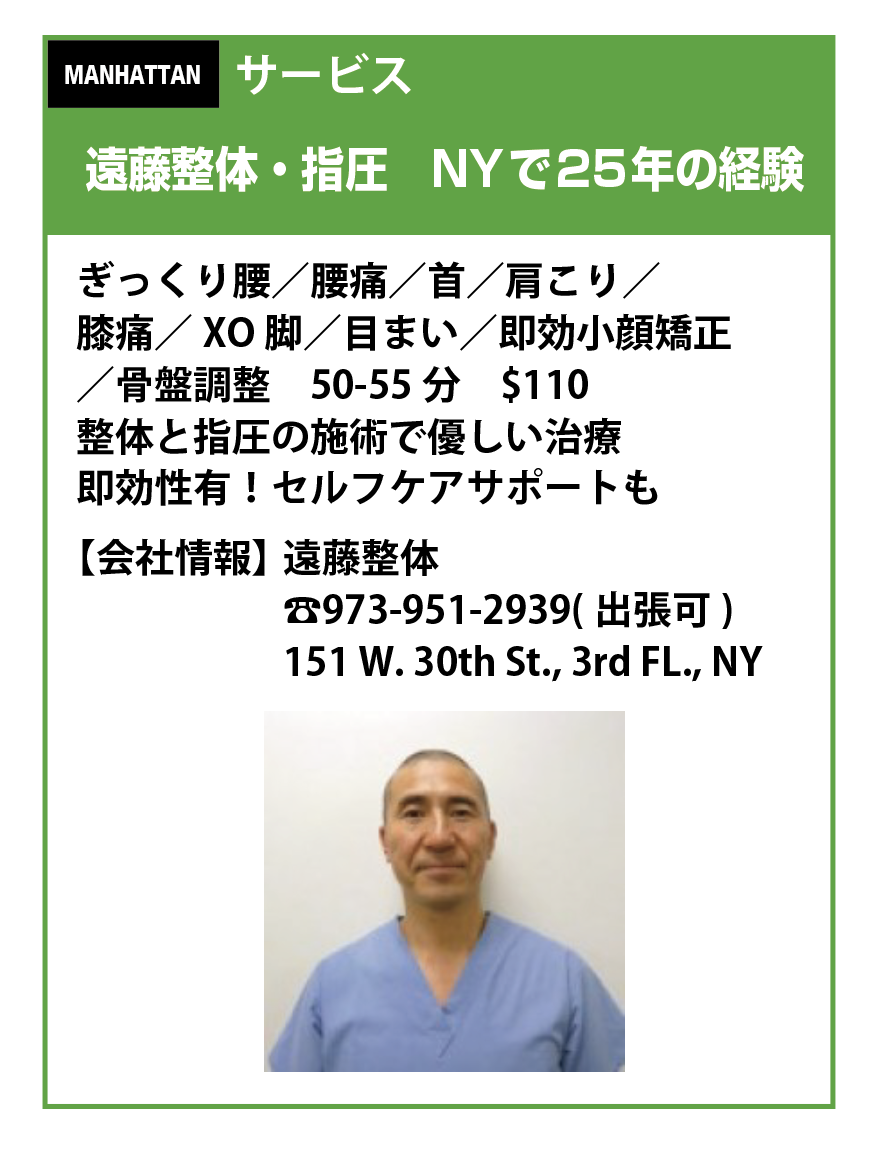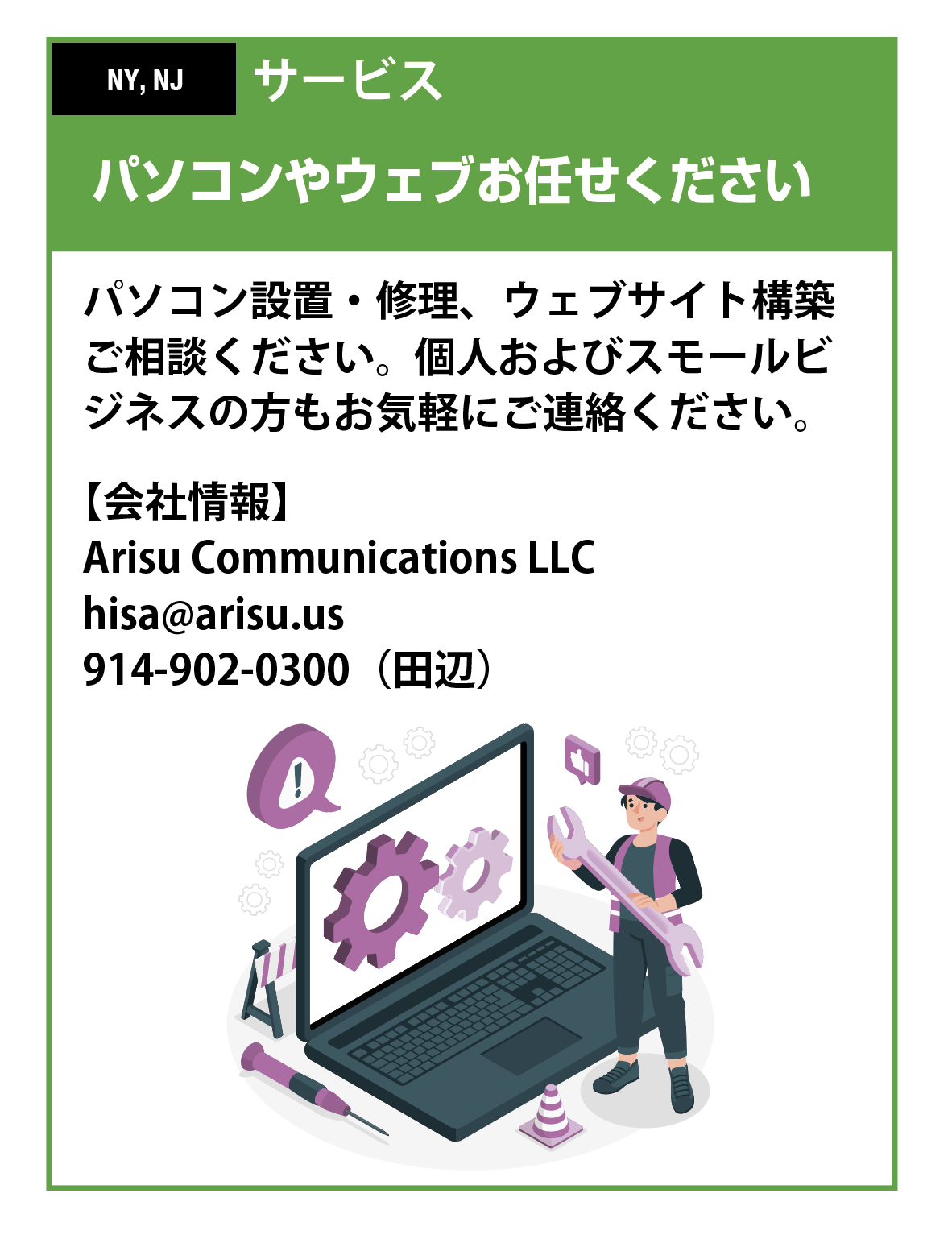連載959 偵察気球で緊張する米中関係!
世界一の「監視国家」になった中国の実態 (中)
古代から行われてきた「戸籍」による監視
中国人は「正義」とか「公正さ」とか「法」とかを信じていない。それが欧米と決定的に違うところだ。中国人が信じているのは「地縁、血縁」、そして「お金」だけだ。その繋がりのなかで人生が成り立っている。そして、中国人がもっとも大事にするのが、「面子」(メンツ)である。
これは大昔から変わらない中国人の世界観で、この世界観はなぜか現代のハイテク監視文化に馴染む。いまの中国には、どこに行っても監視カメラがあり、その数5億4000万台に上り、これに顔認証システム、電話トラッカーなどが組み合わされているので、誰がどこでなにをしているのか、すべてが当局に把握される。
住民の監視は、古代で言えば「戸籍」である。中国で戸籍が誕生したのは、紀元前4世紀の秦においてで、秦は富国強兵のために「什伍(じゅうご)の制」をつくった。
これは、集落の住民を「10人組(什)」と「5人組(伍)」に分け、それぞれ相互に監視させて連帯責任を負わせる制度で、これにより王は住民をうまく統治でき、徴兵もたやすくできるようになった。
その結果、始皇帝の時代に秦は一大強国となって天下を統一した。この後、中国ではどの王朝も、戸籍による住民監視を行ってきた。宋代の「保甲法」、元代の「千戸制」など、いまに置き換えればみな「監視システム網」である。
秦の時代に逆戻りした「十戸長」制度
考えてみれば、日本の戸籍制度は、中国の制度を見習ってできた。日本最初の戸籍とされる飛鳥時代の「庚午年籍」(こうごねんじゃく)は、唐のシステムのパクリである。
中国共産党も、歴代王朝と同じように、統治を強化するために戸籍制度(戸口:フーコオ)をつくった。これにより、住民は都市戸籍者と農村戸籍者に分けられ、統治者が容易に監視できるようになった。
なにしろ、中国の戸籍には、学校の成績や共同体のなかでの行動などが紐づけられていて、ネット社会になる前から、中国人にはプライバシーはほぼなかった。
昨年、四川省内江市が「十戸長」制度を推進するというニュースが、中国国内でも話題になった。「このネット時代に秦の時代に逆戻りか」と、ネット民は騒いだ。なぜなら、「十戸長」とは、十戸(10世帯)ごとに1人の管理人(十戸長)を選び、管理人が住民を監視するというものだからだ。
このようなシステムにより、中国のゼロコロナ政策は徹底された。管理人は、出入りする住民の調査やスマホの健康管理アプリのチェックを行う。中国では、スマホに「行程?」という健康管理アプリを入れておかないと、どこにも行けない。
このアプリで濃厚接触などがわかると、即座に隔離された。もし、十戸長がこうしたことを怠ると、所属する十戸(十世帯)全員の連帯責任となる。
監視社会では誰もが信号を守る
私はコロナ禍以前の中国しか知らないが、中国の監視社会はコロナ禍以前にすでに十分に出来上がっていた。
監視社会がどういうものか、中国人の変わりように驚いたことがある。
たとえば、上海。昔、この街では、誰も信号など守らなかった。クルマも赤信号に代わる間際までクラクションを鳴らして突っ込んできた。横断歩道で信号が赤のとき、クルマが来ていなければ、誰もが信号を無視して横断した。これはアメリカ、NYのマンハッタンでも同様だ。
しかし、いまの上海では、誰もが信号が代わるまでじっと待っている。日本人ならほぼみなそうすることを、いま中国人がやるようになった。
驚くのは、タクシーに乗ったら必ず「シートベルトをしてくれ」と言われることだ。昔はほぼ誰もシートベルトなどしていなかったのに、いまや助手席、後部座席に乗っている誰もがしている。そして、信号を必ず守る。
なぜか? それは、たとえ深夜で誰も見ていなくても、監視カメラが見ているからだ。信号無視は罰金である。飲酒運転などになれば即刻刑務行きである。日本ではいまも
「あおり運転」が跡を絶たないが、そんなことをすればすぐに公安がやってきて逮捕される。
監視社会とはこういう社会で、交通違反はもとより、中国では犯罪が劇的に減った。
(つづく)
この続きは3月14日(火)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで