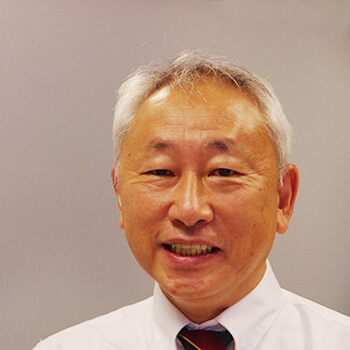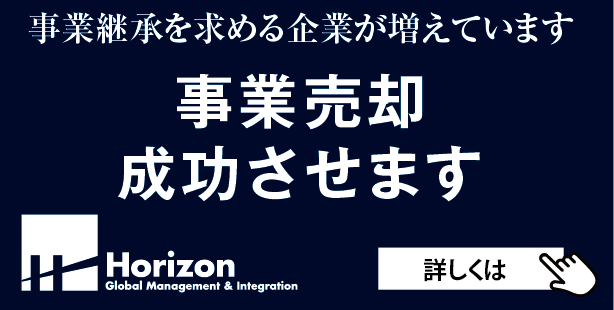連載1039 中国デカップリングは日本を確実に貧しくする。 耐えられるのか、日本経済? (完)
(この記事の初出は2023年6月13日)
インド、ASEANにおいては脱中国は不可能
現時点で、日本の貿易は輸出入とも中国が断然の1位である。日本企業のサプライチェーンは、中国からの素材や部品や台湾からの半導体の輸入に大きく依存している。
たとえば、日本への電機電子製品の輸入において、中国のシェアは現在約45%である。これは、50%を超えていたピーク時よりは減少傾向にあるとはいえ、まだまだ高い。
また、自動車部品の輸入においても 中国のシェアは40%を超えている。
つまり、現時点で、日本の基幹産業は、中国なしでは成り立たないのだ。この状況で、脱中国を果たすということは、日本経済が立ちいかない、日本が貧しくなるということを意味する。中国からの素材や部品の輸入がなくなれば、その経済的損失は輸入額だけには収まらない。下流の企業の生産も滞り、その影響は全サプライチェーンを通じて増幅される。
このように、中国デカップリングは、輸出市場の縮小と輸入価格の上昇などを通じて、低迷に陥っている日本経済に追い討ちをかける。日本の先進国転落を加速させるだけになる。
それでも、日本が中国デカップリングを果たせなければならないなら、代替地はフレンドショアリングのIPEF14カ国が中心になる。しかし、インドのリスクは中国以上に高く、中国とは経済的に繋がっている。
また、 ASEAN諸国は、中国に比肩する素材や部品の製造はできていないうえ、もはや中国経済圏と言っていいほど中国依存度が高い。それに、彼らは米中日の援助で国を発展させようとしており、こうした「3つ股政策」を放棄しようとしないだろう。
アメリカが提唱する「フレンドショアリング」は、絵に描いた餅で、機能しない可能性のほうが高いのだ。
米トップ企業CEOは脱中国に反対
このように見てくると、今後、中国デカップリングがどこまで進むかは、本当にわからない。しかも、アメリカ自身でさえ、それに耐えられるかはわからない。中国を切り離せば、インフレはますます昂じるだろう。
それにしても驚くのは、イーロン・マスクだ。彼は、5月末に3年ぶりに中国を訪問し、中国高官と会談した。中国メディアが伝えたところでは、北京で中国の秦剛外相と会談したイーロン・マスクは、「中国とアメリカの利益は絡み合っている」「中国とのデカップリングにテスラは反対す流」と述べたという。
このイーロン・マスクの発言は、アップルCEOのティム・クックやゼネラル・モーターズ(GM)CEOのメアリー・バーラと同じだ。ティム・クックは3月の中国訪問時に、「アップルと中国の関係は共生的なものだ」と述べ、メアリー・バーラも、「中国はGMにとって引き続き主要な市場であり、現地のパートナーとクリーンカーの開発を継続する」と述べている。
はたして、こうした動きとアメリカ政府とが繋がっているかどうかはわからない。少なくとも、イーロン・マスクの行動と発言は、バイデン政権の意向とは相反する。しかし、物事には裏と面があることを忘れてはならない。
ロシア敗退で中国外交が変わることも
ウクライナ戦争とともに、台湾有事が現実問題として騒がれ、中国脅威論が増している。日本の保守言論は、盛んに「脱中国」「反中国」を唱えている。彼らは、日本が貧しくなることを覚悟のうえで、そう唱えているのだろうか?
しかも、政府はできもしない反撃能力による防衛力強化に、今後5年間で総額43兆円もつぎ込もうとしている。
しかし、台湾有事には米中ともになんのメリットもない。ウクライナ戦争でロシアが敗退すれば、現在の中国の外交戦略は変化する可能性がある。いままでのように、「戦狼外交」と呼ばれた荒々しい外交スタイルでは、世界から反発を買うだけだ。
デカップリングも即効性はないが、じわじわとは利いてくる。そうなれば、中国のほうから欧米に歩み寄る可能性も捨てきれない。
それを期待しつつ、日本は淡々と、そして戦略的に、脱中国を進めていくべきだろう。
(つづく)
【読者のみなさまへ】本コラムに対する問い合わせ、ご意見、ご要望は、
私のメールアドレスまでお寄せください→ junpay0801@gmail.com

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

春の満月「ピンクムーン」がNYの夜空を幻想的に、 日時やおすすめ鑑賞スポットは?
-

なぜ? アメリカの観光客が減少傾向に「30〜60%も…」、NY観光業で深まる懸念
-

アメリカのスーパーの食材に「危険なレベル」の残留農薬、気をつけるべき野菜や果物は?
-

生ごみのコンポスト義務化、守られず ごみ分別違反に4月1日から罰金
-

トレジョの人気すぎるミニトートに新色、各店舗からは「買えた」「買えなかった」の声 ebayではすでに約16倍の価格で転売!?
-

日本の生ドーナツ専門店「I’m donut?」がついにNY上陸、場所はタイムズスクエア オープン日はいつ?
-

NYで「ソメイヨシノ」が見られる、お花見スポット5選 桜のトンネルや隠れた名所も
-

ティモシー・シャラメの「トラッシュコア」 目茶苦茶で個性的、若者を魅了
-

物件高騰が続くNY、今が “買い時” な街とは? 「家を買うのにオススメなエリア」トップ10が発表
-

NY・ソーホーで白昼に起きた悲劇、ホームレスにガラスで首を刺され…女性が重体