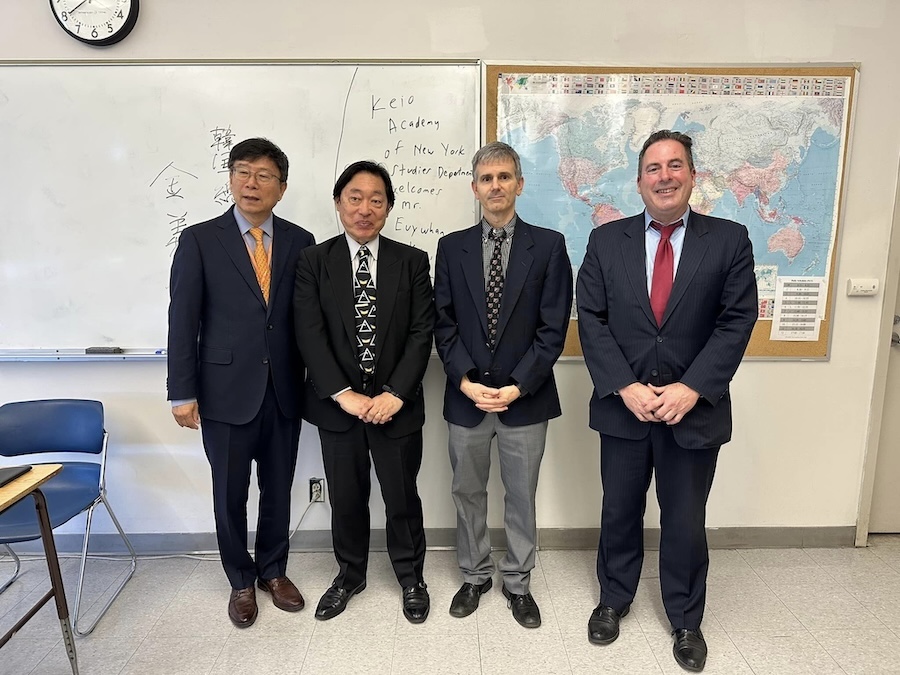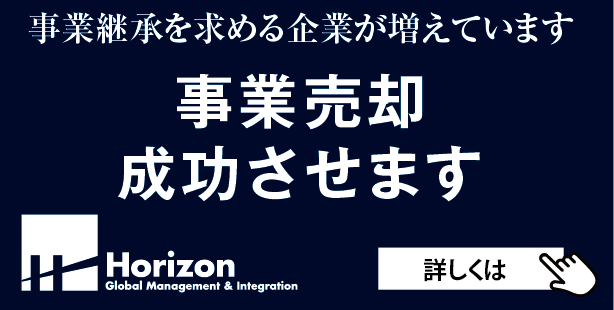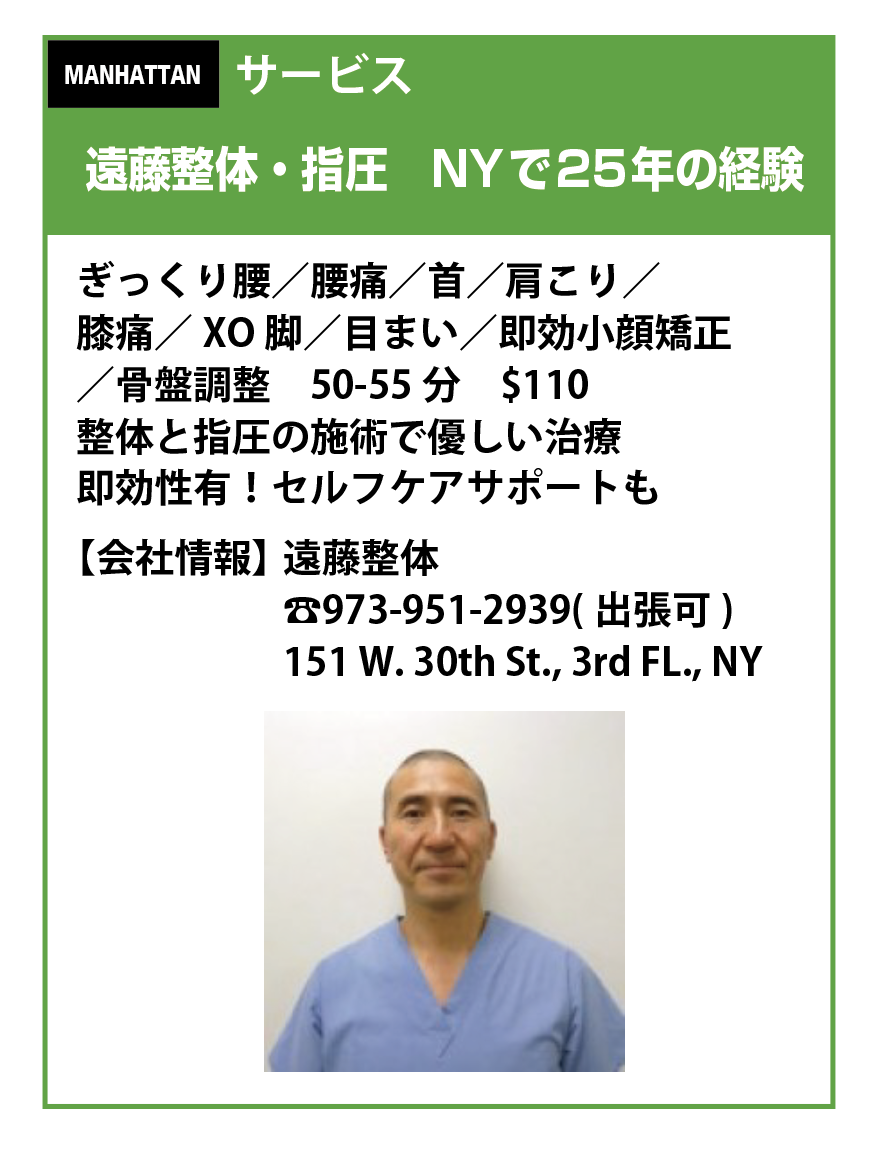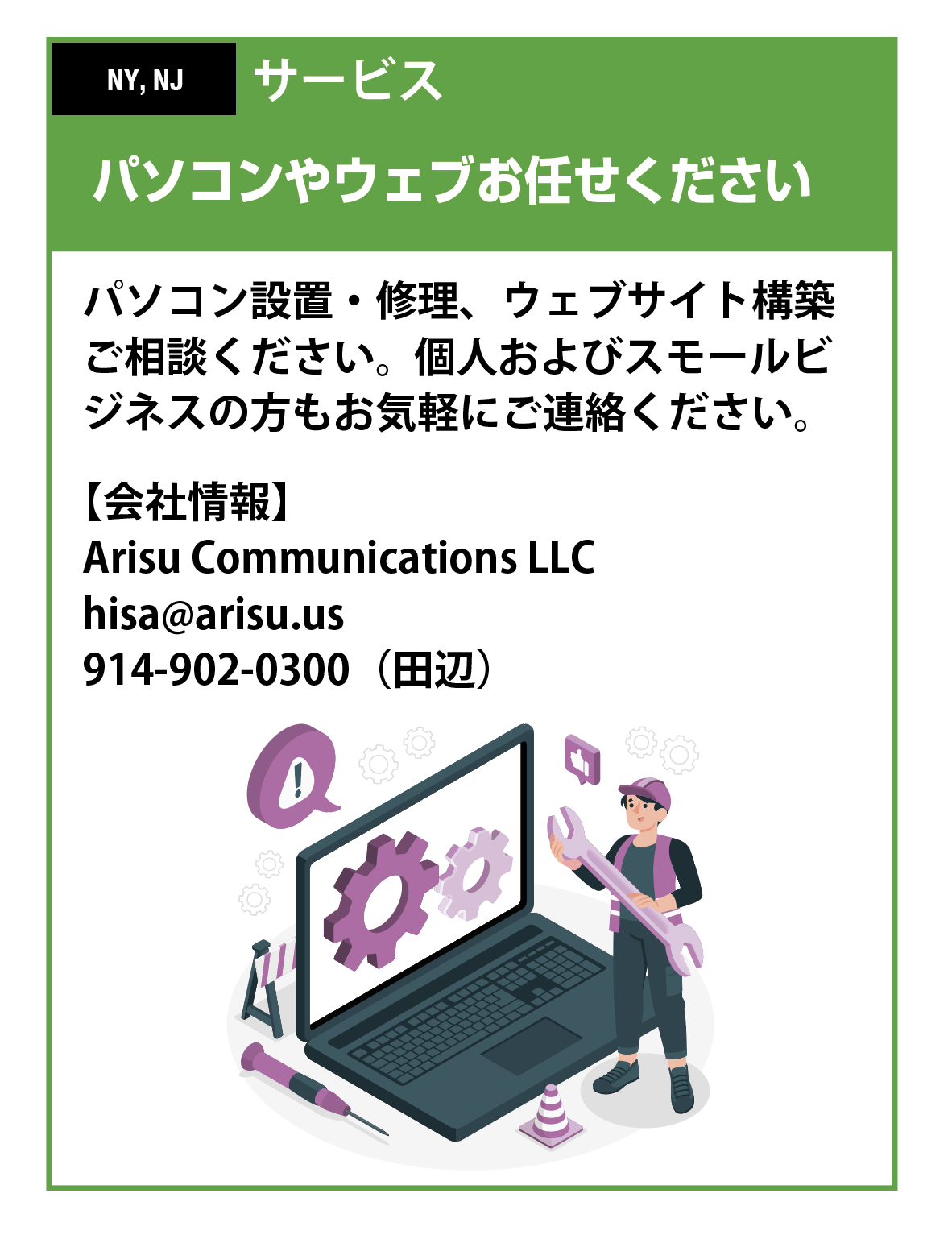連載1057 岐路に立つバイデン・アメリカ
「学生ローン」「人種優遇」停止で経済失速も? (中2)
(この記事の初出は2023年7月7日)
先を急ぎすぎて判断を誤ったバイデン
バイデン政権が学生ローンの債務免除の根拠とした法律は、「2003年学生高等教育支援法」(The Higher Education Relief Opportunities for Students Act of 2003;HEROES法)というもので、通称は「HEROES法」。
この法律により、バイデン大統領は、返済期限の延期も債務免除できるとして大統領令に署名した。なぜなら、トランプ前大統領も、このHEROES法により、コロナ下での学生ローン借り手の経済的負担を軽減するため、学生ローンの債務返済を延期したからだ。
ところが、HEROES法には「ローンの借り手が戦争や軍事的作戦、あるいは国家的な危機に関連して金融的な困難に遭遇した場合、教育長官はローン返済を免除できる」と規定されているだけだった。つまり、返済免除は“国家的危機”でないとできないのだ。
そのため、最高裁では、コロナ感染拡大は“国家危機”に該当するのかどうかが争点となった。教育省はHEROES法に基づく返済免除の権限はあると主張したが、最高裁はこれを認めなかった。
バイデン政権は、先を急ぎすぎたと言えるだろう。返済の延期までならよかったが、債務を免除するには議会での立法が必要だった。ナンシー・ペロシ下院議長も、早くからこの点を指摘していた。「大統領には債務免除の権限はない。延期することはできるが、免除する権限はない。それには議会の決定が必要だ」と述べていた。
バイデン政権発足時は、上下院とも民主党がマジョリティだった。しかし、中間選挙で民主党は下院でのマジョリティを失ったのだから、もっと慎重に政策実現を目指すべきだったのではないだろうか。
背景にある保守派とリベラル派の対立
法的な問題もあるが、このような最高裁判断が出てしまった背景には、最高裁判事の人員構成がある。トランプ前大統領が保守派判事を3人も任命したことで、最高裁は保守派がマジョリティとなったことが影響している。
現在、9名の判事のうち6名が保守派判事である。その結果、最高裁では、リベラル派の主張は退けられ、保守派の主張が通るようになった。2022年以降、最高裁では、保守派の意向に沿った判決が相次いで出ている。
その最大の例は、2022年6月に女性の中絶の権利を認めた最高裁の1973年の「ロー対ウエイド判決」が覆ってしまったことだ。このため、アメリカでは人工中絶が違憲となってしまった。
アファーマティブ・アクションと学生ローン免除の違憲判決は、それに続くもので、ある意味で共和党と保守派の政治的な駆け引きの結果と言える。
最高裁の判事でリベラル派のエリーナ・ケーガン判事は、「反対意見」を提出し、そのなかで、こう述べている。
「最高裁は国の政策の調停者、実際には決定者になってしまっている。最高裁は議会や政府にとって代わって国の政策を策定する結果になる。それは最高裁の適切な役割ではない。民主主義の秩序にとって危険である」
ちなみに、ケーガン判事は、ハーバード大学ロースクールの元学部長で、アメリカ史上4人目の女性最高裁判事だ。
(つづく)
この続きは8月10日(木)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで