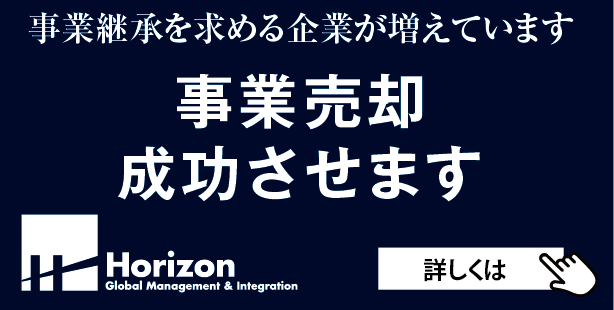連載1099 これでは日本は守れない!
防衛費増額の“支離滅裂”な使途(つかいみち)。 (上)
(この記事の初出は2023年9月26日)
今回は、日本の安全保障について考えてみたい。すでに、岸田政権は軍備増強路線に突入しており、防衛費は5年間で43兆円程度に増額され、来年度はその2年目となる。
増額された防衛費で進んでいるのが、「スタンド・オフ・ミサイル 」の開発、英伊との3カ国共同での次期戦闘機の開発、陸自の装備増強、イージスステム搭載艦の建造などだが、どこをとってもなぜこんなことをするのか、まったくわからない。なにより、軍事的・経済的合理性、技術的な裏づけがない。
こんな日本の軍事予算の使途を見て、中国、北朝鮮は、せせら笑っているに違いない。
誰も聞いていない「核兵器のない世界」
まず、この間行われた岸田首相の国連スピーチから始めたい。どのメディアも同じようなタイトルで報じたので、覚えている方も多いだろう。
たとえば、その一つ、TBSニュースはこう伝えた。
『岸田総理が“核軍縮”に30億円の拠出を表明 「核兵器のない世界」実現に向けた会議体を新設へ』(TBSニュース)
報道内容の要旨は、「私は核兵器のない世界を求めています。その実現に向け、日本は新たに30億円を拠出し、海外の研究機関・シンクタンクに核軍縮に関する議論の場、核兵器のない世界に向けた“ジャパン・チェア”を新たに設置します」というもの。
「バラマキメガネ」と揶揄される岸田首相にとって、30億円のバラマキはたいした額とは言えない。問題は、金額ではなく、「核兵器のない世界」である。アメリカの核の傘の下にいながら核兵器のない世界を世界に訴える。その滑稽さ、幼稚さだ。しかも、このアピールを、ほとんど誰もいない議場、核保有国の首脳は1人もいない議場で言うのだから、馬鹿げている。
岸田首相の頭の中には、この世界の平和が軍事力バランス、とくに「核による抑止力」(nuclear deterrence:ニュークリア・デトーランス)によって保たれている厳然たる事実がないようだ。日本は中国、ロシア、北朝鮮という核保有国の標的になっているのだから、本来なら日本こそが核武装しなければならない。それがしなくて済んでいるは、アメリカの核の傘があるからだ。それもわかっていないのだろうか。
内閣総理大臣は、自衛隊(日本軍)の最高司令官である。岸田首相の言葉は常に軽い、軽すぎる。「核兵器のない世界」が被爆国としての体裁のためだけのためでなく、本気で言っているのだとしたら、彼には日本の安全保障は託せない。
過去最大の7兆7385億円が計上される
私は軍事の専門家ではないので、ここから述べていくのは、その筋の専門家の話を総合した見解である。彼らは、大手メディアでは本当のことを言わない。国防に関して批判的なことを言えば、ほぼ仕事がなくなるからだ。
すでに、8月の末時点で2024年度予算の概算要求は締め切られ、防衛費は、2023年度当初予算を1兆1384億円上回る過去最大の7兆7385億円が計上されることが決まった。昨年、岸田内閣は今後5年間で、防衛費を従来の1.6倍の43兆円程度を支出することを決めており、今年度予算からそれが実行されている。よって、今回の2024年度予算は2年目であり、その使途は既定路線上にある。
*今回の防衛予算の中身について詳しく知りたければ、防衛省のHPにある「防衛力抜本的強化の進捗と予算」を見てほしい。
https://www.mod.go.jp/j/budget/yosan_gaiyo/2024/yosan_20230831.pdf
では、この予算のなにが問題か?
予算案に沿って使途を一つ一つチェックしていくと、一体この政府はなにを考えているのかわからなくなっていく。
というより、これで本当に日本が守れるのかと、専門家でなくとも思う。
つまり、防衛費の増額は日本の安全保障の強化につながらず、税金の壮大な無駄と言えるのだ。以下、それを指摘していきたい。
(つづく)
この続きは10月31日(火)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

春の満月「ピンクムーン」がNYの夜空を幻想的に、 日時やおすすめ鑑賞スポットは?
-

なぜ? アメリカの観光客が減少傾向に「30〜60%も…」、NY観光業で深まる懸念
-

アメリカのスーパーの食材に「危険なレベル」の残留農薬、気をつけるべき野菜や果物は?
-

生ごみのコンポスト義務化、守られず ごみ分別違反に4月1日から罰金
-

トレジョの人気すぎるミニトートに新色、各店舗からは「買えた」「買えなかった」の声 ebayではすでに約16倍の価格で転売!?
-

日本の生ドーナツ専門店「I’m donut?」がついにNY上陸、場所はタイムズスクエア オープン日はいつ?
-

NYで「ソメイヨシノ」が見られる、お花見スポット5選 桜のトンネルや隠れた名所も
-

ティモシー・シャラメの「トラッシュコア」 目茶苦茶で個性的、若者を魅了
-

北米初のユニクロ「カフェ」がNYにオープン、気になるメニューや価格は?
-

物件高騰が続くNY、今が “買い時” な街とは? 「家を買うのにオススメなエリア」トップ10が発表