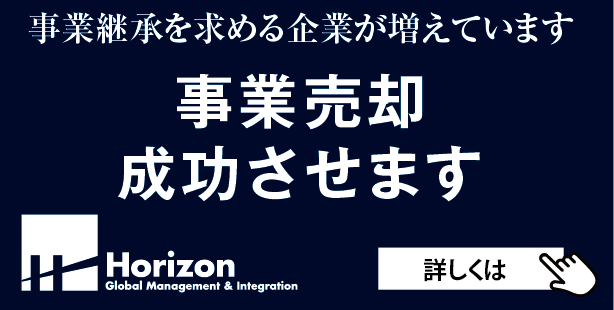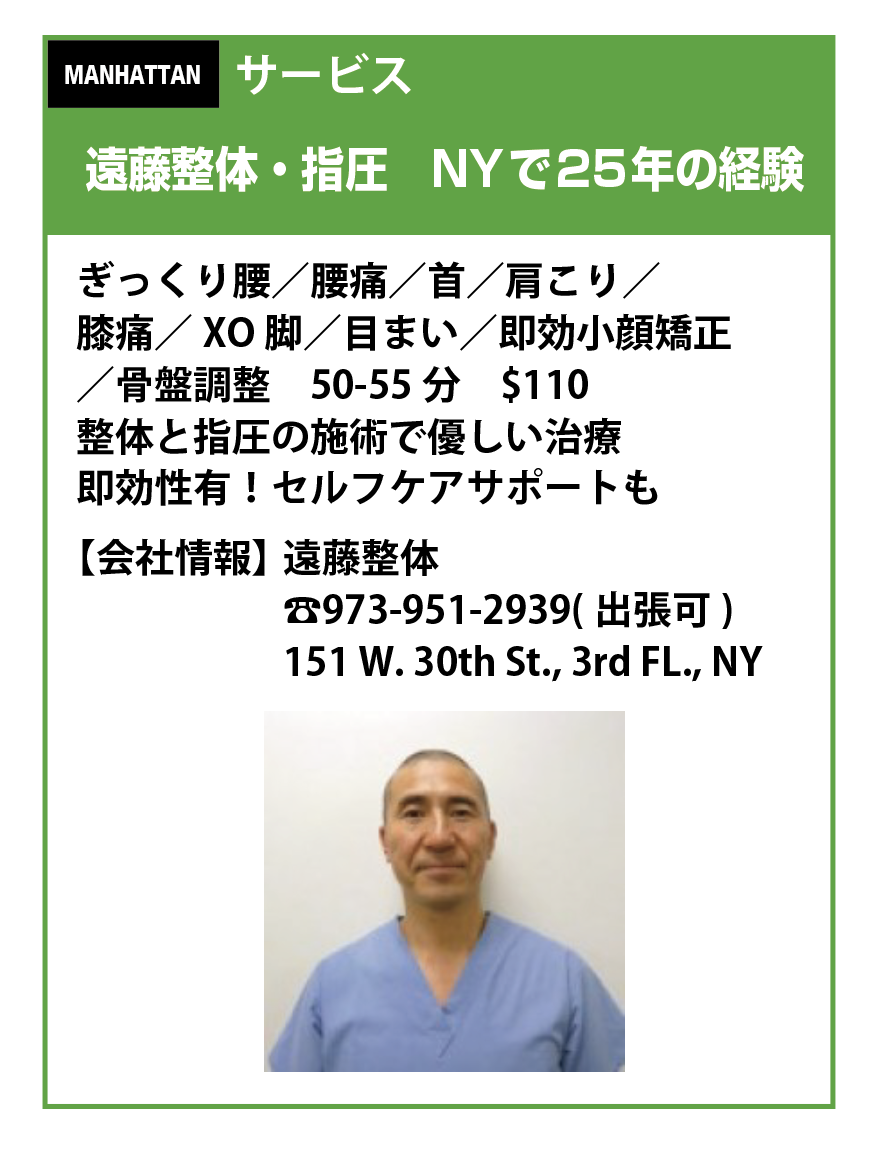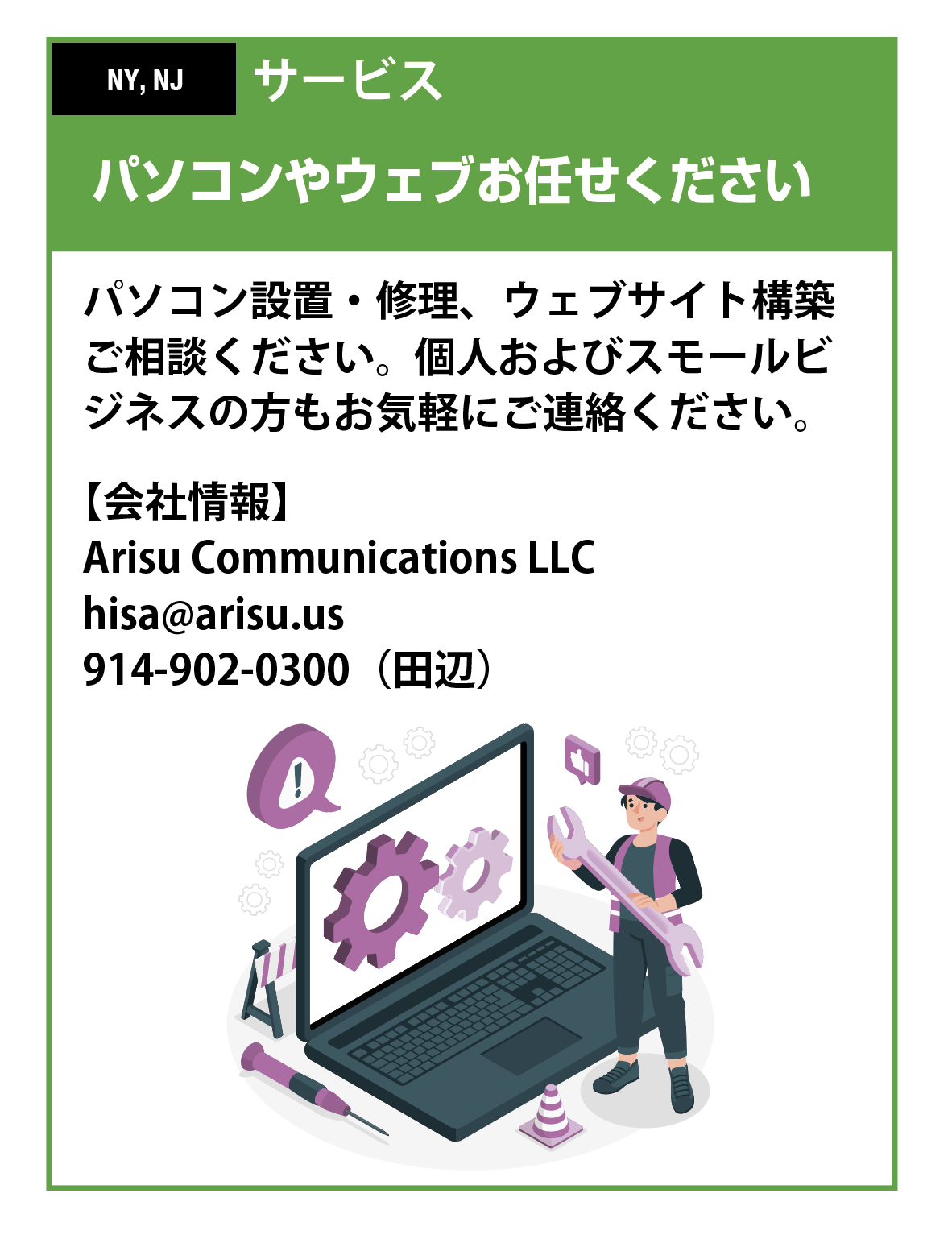連載1101 これでは日本は守れない!
防衛費増額の“支離滅裂”な使途(つかいみち)。 (中2)
(この記事の初出は2023年9月26日)
ついこの前までドローンと言えば災害用
陸上自衛隊は、いまだに冷戦時代の戦略、北海道でソ連と戦う絵空事から抜け出せていないと言うほかない。この“石器時代思考”は、全自衛隊に及んでいる。
その弊害が、ドローンの軽視だ。
驚くべきことに、これまでの自衛隊には、ドローン部隊がなく、そうした現代兵器を駆使する情報システムもなかった。
今回の防衛費増額でようやく、ドローンの大量導入、ドローン部隊の整備が決まったが、その予算額はあまりに少なく、まだ試行段階というのだから情けない。
今年の7月、海上自衛隊八戸航空基地で、やっと無人偵察機「シーガーディアン」の運用テストの模様が報道陣に公開された。シーガーディアンは、現代戦には必須の戦力だ。
自衛隊がドローンを本格的に使い出したのは、2018年9月に発生した北海道胆振東部地震からである。しかし、それは被災状況の確認のためで、災害用だった。自衛隊は、ついこの前までドローンを武器とは考えていなかったのだ。
南西諸島での戦いは間違いなくドローン戦
今年度から始まった防衛費増強は、2022年12月に決定された「防衛3文書」に基づいている。この文書に「無人アセット防衛能力の強化」という項目があり、これで初めてドローンの整備が打ち出された。
その第1弾として、今年度からウクライナ戦争で活躍しているアメリカ製特攻自爆ドローンの「スイッチブレード」や、対戦車攻撃を得意とするトルコ製の「バイラクタルTB2」、さらにイスラエル製の対レーダードローン「ハロップ」などが試験導入された。しかし、本格的な配備は2025年とされている。
南西諸島で戦争が起これば、それはドローン戦になるのは間違いない。海上自衛隊の艦艇に、“チャイニーズ・スイッチブレード”と言われる自爆ドローン「蜂群」が、飽和攻撃を仕掛けてくるだろう。
「スタンド・オフ・ミサイル」開発が目玉
本当に耳を疑うのが、「スタンド・オフ防衛能力」として国産ミサイルを開発・整備することだ。これに、莫大な予算をつぎ込む。スタンド・オフ・ミサイルを保持することには異論はない。しかし、なぜ、国産でなければいけないのか?
「スタンド・オフ」とは「離れている」という意味で、「反撃能力」の保持を目的として、敵の射程圏外から攻撃できるというのが「スタンド・オフ・ミサイル」である。
これを、現在陸自が配備している「12(ひと・に)式地対艦誘導弾」(地上発射型の対艦攻撃ミサイル)を改良して開発・製造しようというのである。12(ひと・に)式の現在の射程は100〜150キロで、これは地対艦ミサイルだ。つまり、近づいてくる敵艦船に対して地上から発射する。この射程を10倍に伸ばして1000キロを超えるようにするというのである。
そうすれば、九州や南西諸島から発射して大陸まで届く。
すでに開発に入ったのが、「能力向上型(地発型)」と離島防衛用の「高速滑空弾」で、納入は2026年および2027年になるという。また、能力向上型では艦発型と空発型も開発し、さらに潜水艦発射型誘導弾の開発も進めていくという。
そこで、これのなにが問題かと言えば、開発・製造するのが三菱重工、川崎重工で、国産にこだわっているという点だ。
防衛省はすでに、今年の6月に、「スタンド・オフ・ミサイル」の研究・開発4事業について、三菱重工、川崎重工と契約したと発表している。その契約総額は、約3147億円と公表された。
(つづく)
この続きは11月2日(木)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで