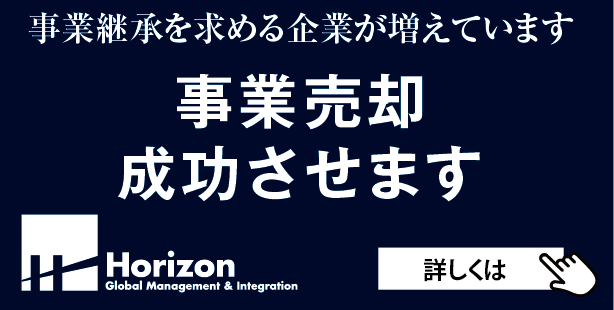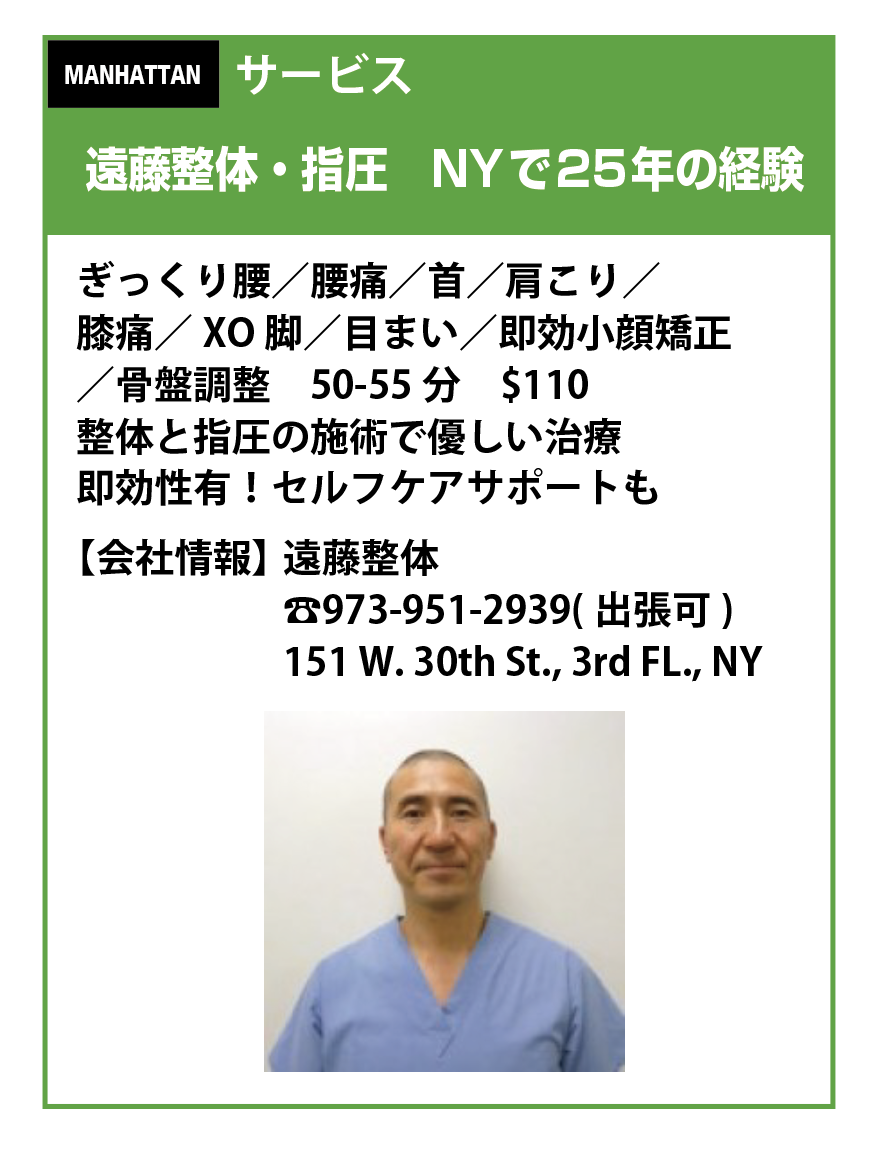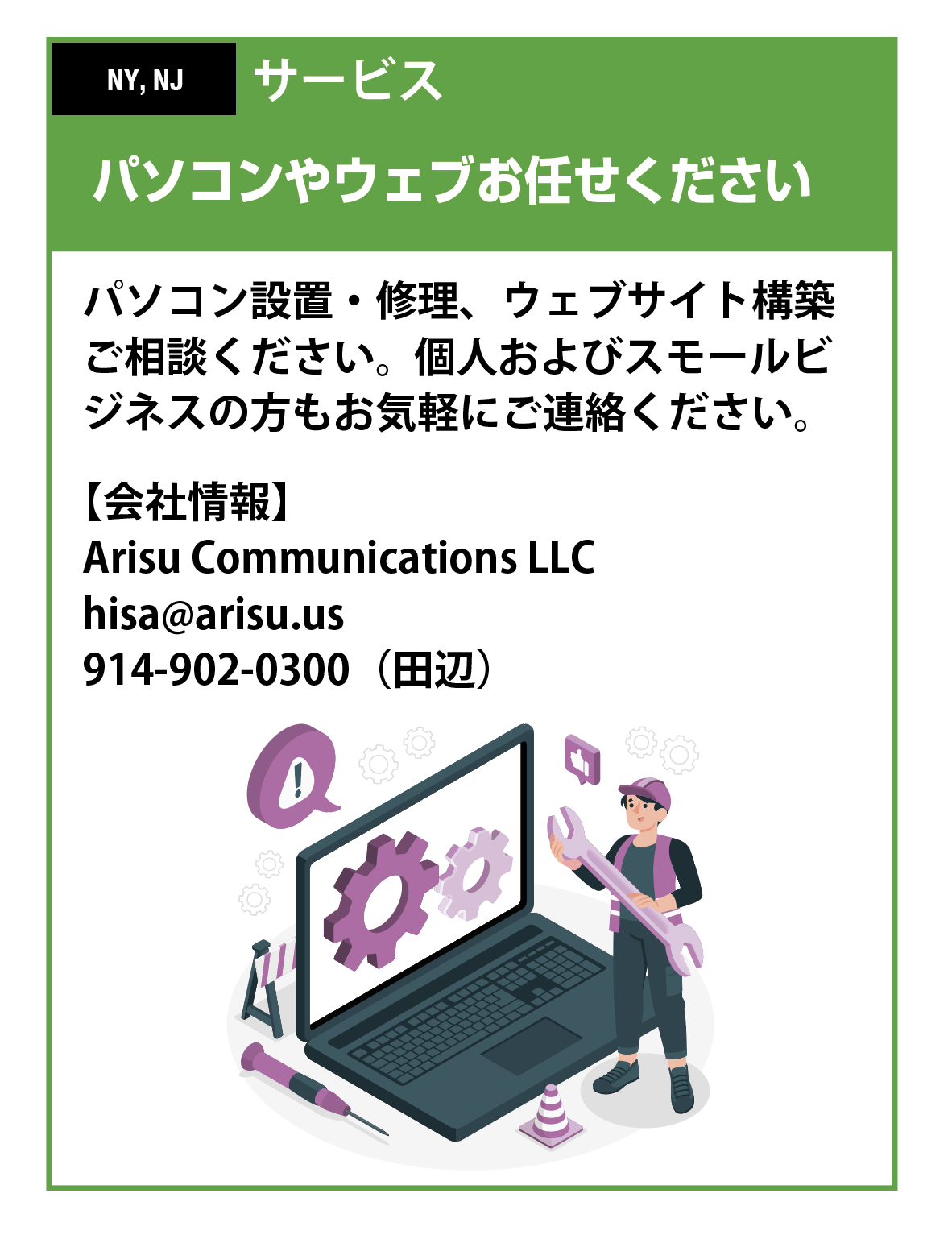連載1111 負けがわかっていても突き進む
大阪万博は「インパール作戦」「本土決戦」なのか? (中1)
(この記事の初出は2023年10月10日)
招致した人間たちの「超楽観」に驚く
岸田首相の「開催宣言」により、ホッとしたのが日本維新の会である。もちろん、大迷惑なのは国民だ。当初の1250億円から約2倍に増えた開催費用の2300億円への税金投入は決まったも同然となったからだ。
もちろん、費用はさらに膨らむのは間違いない。最近になって、警備費に200億円などと言い出したから、軽く3000億円を突破するだろう。
さらに、財務省や経済産業省などから幹部職員たちも、ブーイングとなった。ここにきて、万博協会に派遣され、必死になって参加国や建設業者を説得し、開催にこぎつけなければならなくなったからだ。しかし、会場整備とパビリオン建設の遅れは、もはや致命的な状況になっている。
なにしろ、建設が始まったのは、日本館と大阪府・市のパビリオン、日本が参加国に提供する「タイプB」と「タイプC」(この後に説明)、そしてパビリオン会場を円形で取り囲む「リング」だけ。海外の参加国が独自で建設する「タイプA」は、まだ1館足りとも始まっていない。
7月末時点で、基本計画書を出した国はたった7カ国。そのなかからチェコが9月19日、同22日にモナコが仮設建築物許可申請書を大阪市に提出した。このうちチェコに対しては、10月2日に大阪市が申請を許可したことが発表された。
よって、今後は建築確認申請を行い、これが許可されれば着工という段取りになる。
「タイプX」という苦肉の策も通用せず
協会によると、今回の万博には153の国・地域が参加を予定しているという。これらの国・地域は、次の3パターンにより、万博の華とされるパビリオンを建てることになっている。
(タイプA)各国・地域が費用負担をして独自に建てるもので、56の国・地域が計画していると発表されている。
(タイプB)万博協会が建てた施設を国・地域ごとに借り受けるもの。
(タイプC)万博協会が建てた施設の一部を国・地域が共同でシェアするタウンハウス形式。
前記したように、「タイプA」の建設は、さまざまな理由から大幅に遅れている。そのため、8月半ば、協会は協会自体が建設を代行するプレハブの「タイプX」を参加国に提案した。日本側が業者を連れてきて、なんとか建てますから参加してくださいというのだ。「タイプA」参加国のうち、建築業者を確保できているのは半数に満たないというから、これはまさに苦肉の策だった。
「タイプA」断念で空き地だらけになる
「タイプA」から「タイプX」に移行すれば、オリジナルなパビリオンはできないが、日本側が全部お膳立てしてくれる。ならばそれでいいという国・地域が出てくるだろうと、協会は考えた。ところが、大阪万博に対する世界の関心は薄く、打診してきた希望国は、現時点で10カ国にも達していないという。
さらに悲惨なのは、「タイプA」による独自パビリオンを止めて、「タイプX」ではなく「タイプC」へ移行した国が出たことだ。協会は、「タイプC」はスペースにある程度余裕があるので、「タイプA」参加国の移行を認めることにしたのである。
そうしたら、さっそくスロベニアが 「タイプC」に移行することを表明した。
「タイプA」から「タイプC」に移行するというのは、家を建てるつもりが建売住宅すら諦めて、手狭なマンションを借りつというぐらいの大転換である。いくらプレハブとはいえ戸建の建売住宅と言える「タイプX」すら選ばないのである。
おそらく、今後も「タイプC」移行組は続出するだろう。
もし、計画されているという「タイプA」の海外パビリオンのうち、半数ほどしか建たなかったらどうなるだろうか? 巨大な円形リングの内側の敷地が、空き地だらけになってしまう。この件を取材したメディアに、協会幹部の1人は、こう答えたという。
「パビリオンが建たない場合は、その敷地を来場者向けの休憩所にしたり、緑を植えたりなどの活用法も検討する」
こんな万博に誰が行くのだろうか?
(つづく)
この続きは11月16日(木)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで