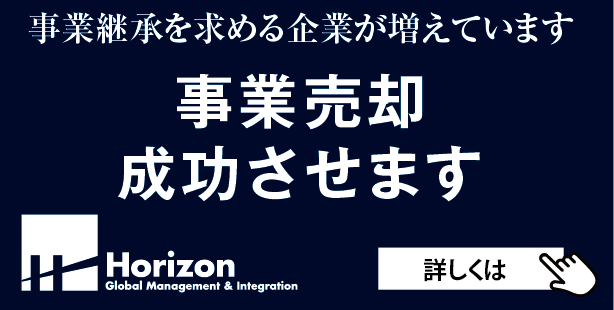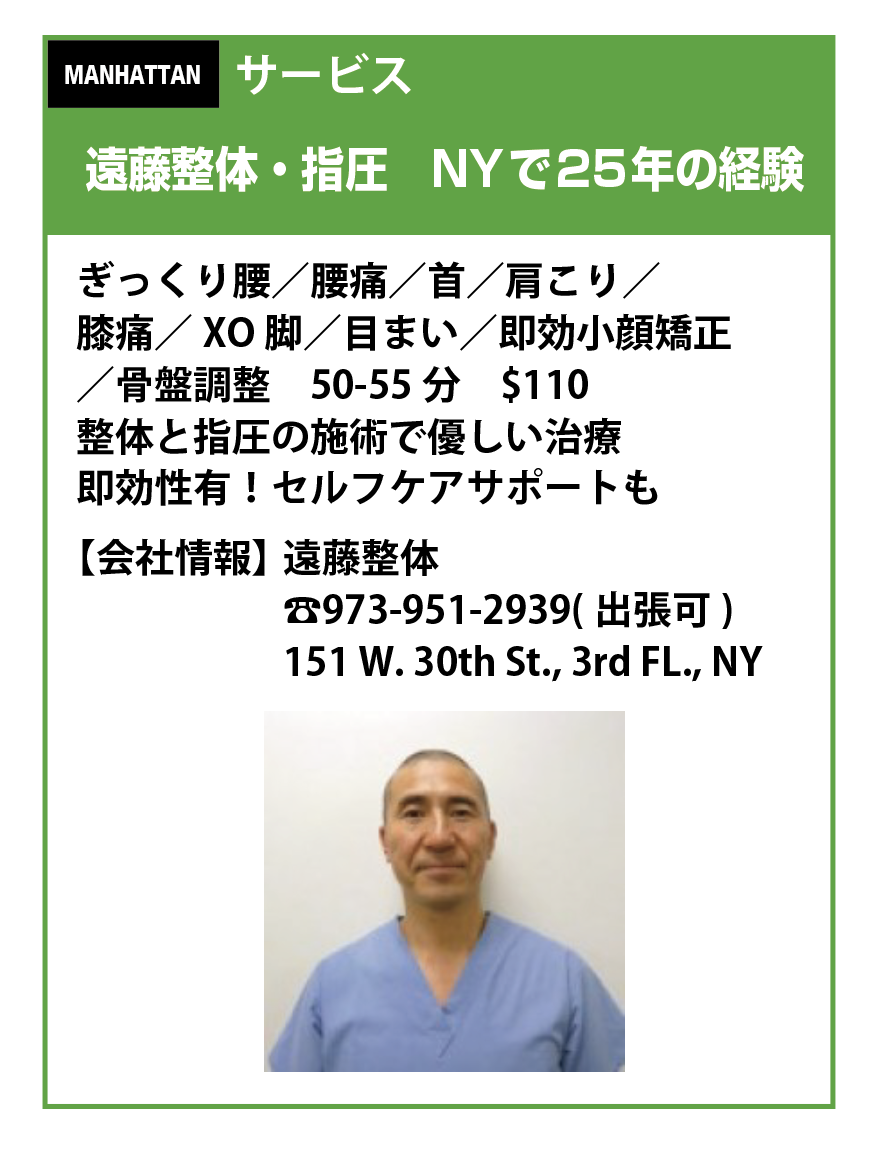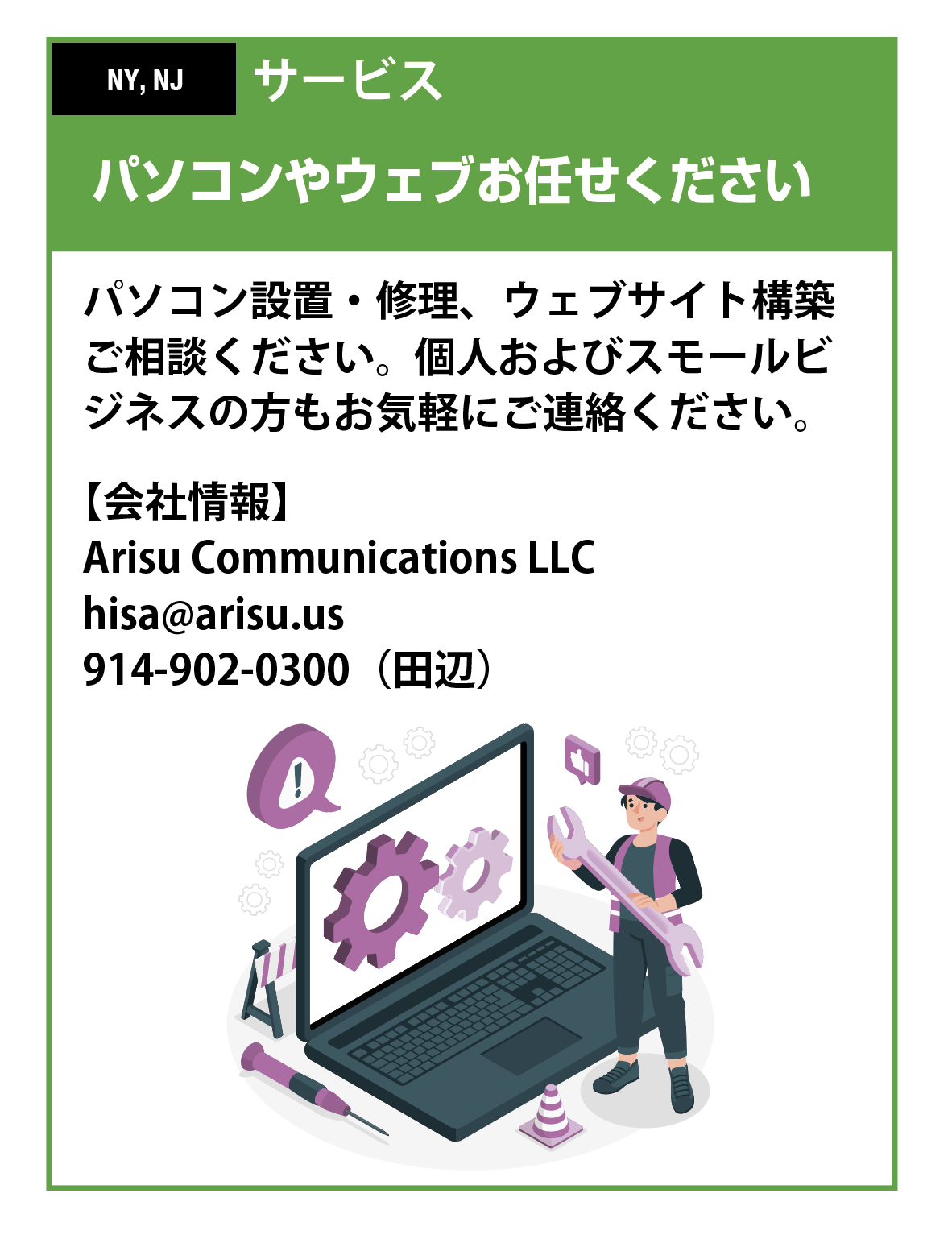連載1117 メディアはなぜ「朗報」と言わないのか?
2030・34札幌冬季五輪招致“大失敗”の裏事情 (中)
(この記事の初出は2023年10月17日)
幻となった「2030札幌内定」スクープ報道
ここで思い出してほしいのが、つい2年前には、2030年札幌開催が「ほぼ内定」していたことだ。
2022年1月1日、まさに正月の元旦に、共同通信は『2030年冬季五輪、年内にも内定 札幌本命、IOCと協議』というスクープ記事を配信した。
以下、その記事を引用する。
《札幌市が招致を目指す2030年冬季五輪を巡り、国際オリンピック委員会(IOC)のバッハ会長らと日本側が今後の開催地選定の日程などについて21年12月に水面下で協議していたことが31日、分かった。
複数の関係者によると、IOCによる候補地の一本化の時期は現時点で22年夏から冬ごろと見込まれている。札幌は開催実績や運営能力への評価が高く本命視されており、同年中に事実上、開催が内定する可能性もある。住民の支持を得られるかどうかが鍵となる。》
いまとなれば、この報道は幻である。しかし、あの時点では、日本側とIOCとの間では札幌開催で話がついていたのは確かだ。
なぜなら、札幌のライバルとされるバンクーバー(カナダ)、ソルトレイクシティ(アメリカ)は市民の反対が強くて乗り気ではなく、バルセロナ&ピレネー(スペイン&アンゴラ共同開催)は財政難が指摘されていたからだ。
それが、なぜ、この2年で一変してしまったのだろうか?
1年間にわたる「啓蒙活動」の結果は?
2022年の1年間、コロナ禍の渦中にも関わらず、IOCの”お墨付き”をもらった札幌市とJOCは、市民に対する「啓蒙活動」をやり続けた。
それは、根強い反対の声をなんとか封じ込め、招致ムードを高めるためだった。反対の声の中心は、東京五輪を踏まえて「これ以上の税金の無駄遣いは許せない」ということだった。
そのため、札幌市は2021年11月に、当初予算(2019年の試算)の経費を最大900億円圧縮し、2800〜3000億円とするという新たな大会概要案を公表した。その内訳は、施設整備費が800億円、大会運営費が2000億~2200億円で、大会運営費はIOC負担金とスポンサー収入、入場経費等で賄い、税金は投入しないと明記されていた。 秋元市長は、これで反対の声も収まるだろうと考えた。
したがって、この案を踏まえて、1年間にわたる市民啓蒙活動が始まった。「子どもワークショップ」が開催され、その後「市民ワークショップ」「市民シンポジウム」などと名付けられたイベントが、コロナ禍もあって主にオンライン開催で行われた。
しかし、招致ムードは高まらないばかりか、逆にどんどん盛り下がった。
国民の怒りを買った「東京2020」不祥事
招致ムードが減退した主原因は、やはり、「東京2020」の不祥事の発覚である。
2022年8月17日、大会スポンサー企業から賄賂を受け取った容疑で、大会組織委員会元理事の高橋治之氏(元電通)が東京地検特捜部に逮捕された。これを機に、事件は複数のスポンサー企業や大手広告会社に広がり、テスト大会を巡る談合事件まで発覚。「東京2020」が、賄賂まみれの利権大会であったことがはっきりした。
しかも、「東京2020」は大赤字。不祥事発覚の1カ月半前、6月30日に組織委員会は解散したが、それと同時に公表されたのが、最終報告書による“負のレガシー”である。なんと、大会経費は、当初の倍の約1兆4238億円に膨らんでいた。
当初、東京五輪の経済効果は6兆円に上ると言われていたが、コロナ禍のためほぼ消滅したうえ、赤字だけが残ったのである。
さらに、「東京2020」のために建設された施設は、今後、毎年赤字を垂れ流し、それを国民や都民が負担しなければならなくなった。たとえば、国立競技場は毎年約24億円の赤字、東京アクアティクスセンターが毎年6億4000万円の赤字といった具合で、これら一連のことが、国民の怒りを買わないわけがない。
「札幌五輪などいらない」という声が、ますます強まることになった。
(つづく)
この続きは11月28日(火)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで