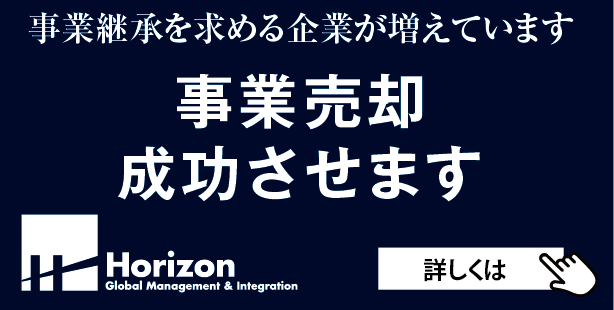連載1118 メディアはなぜ「朗報」と言わないのか?
2030・34札幌冬季五輪招致“大失敗”の裏事情 (下)
(この記事の初出は2023年10月17日)
ボッタクリIOCにとって札幌は“いいカモ”
「東京2020」で、もう一つはっきりしたことがある。
それは、IOCが金権組織で、開催都市、開催国を食い物にしているということだ。トーマス・バッハ会長に、“ボッタクリ男爵”というあだ名がついたことを、いまさら、書くまでもないだろう。
このIOCのボッタクリ体質と、経済効果が望めないことがわかってきたことで、五輪開催(夏季、冬季ともに)に手をあげる都市は、近年、激減した。
たとえば、成功したとされる2012年のロンドン大会では、インバウンド効果が期待されたが、例年以上のおカネは落ちなかった。海外からの観戦客は来たものの、それはもともとのビジネス客、観光客が置き換わっただけで、ホテル収入などはイーブンに終わっている。
だから札幌は、IOCにとっては、“いいカモ”だった。「東京2020」同様にボッタクリができると、そう考えて、2021年12月に、ローザンヌにやってきた札幌五輪招致委員会の“お歴々”に、開催OKの墨付けを与え、それが2022年正月の共同通信のスクープにつながったのである。
しかし、「東京2020」の不祥事発覚によって、情勢はガラリ一変した。
「五輪憲章」を変えてまでボッタクリを継続
ボックタクリが見え見えになったIOCは、近年、危機感を深めてきた。いまや、黙っていてもどこかが五輪をやってくれるような時代ではなくなってしまった。なにもしなければ、手をあげる都市はなくなる可能性がある。
ならば、なんとか打開策を見つければならないと、IOCは考えた。そうして行き着いのが、「複数年の開催地の同時決定」と「時期にとらわれない決定」である。
その結果、早々と決まったのが、2032年の夏季五輪のオーストラリア、ブリスベン開催である。IOCは、のこのこと手をあげたブリスベンを1本釣りにしたのである。
五輪開催地の決定は、五輪憲章により原則として7年前と定められていた。しかし、IOCは、五輪憲章から「7年前とする」規定を削除してしまった。
さらに、IOCは、複数の国や地域、都市にまたがって開催できるようにも、規定を変更した。一国、一都市では、莫大な予算を計上できないと考えたからだ。さすが、“ボッタクリ男爵”がトップを務める組織である。
このIOCの「ボッタクリ」の罠に、自ら進んではまろうとしていたのが札幌だったわけだが、「東京2020」不祥事発覚がIOCの認識を変えてしまった。「これはまずい。これでは札幌からの多大な見返りは期待できない」「ボッタクリは無理」と、IOCは判断したのだ。
内定取り消しで「招致活動の休止」を宣言
こうしてIOCは、昨年12月6日、2030年五輪開催地の決定時期を先送りすると発表した。2020年12月に、札幌に与えた「内定」の“お墨付き”を、事実上、取り消したのである。
IOCは、先送りの理由を「気候変動対策などへの協議のため」と発表した。しかし、これは表向きの理由で、札幌は「おいしくない」「うまくいかない」と判断したからに間違いない。こうして2030年冬季五輪候補地から札幌は消え、開催地選びは振り出しに戻った。
“お墨付き”を失った札幌市は、2022年12月20日に、秋元市長が「積極的な招致活動の休止」を宣言した。「東京2020」の不祥事捜査が続くなかで、これ以上招致活動を続けると、さらに反発を買うと判断したのである。
実際、この宣言の前に行われた世論調査では、札幌市民の67%、道民の61%が「反対」を表明していた。
(つづく)
この続きは11月29日(水)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

春の満月「ピンクムーン」がNYの夜空を幻想的に、 日時やおすすめ鑑賞スポットは?
-

なぜ? アメリカの観光客が減少傾向に「30〜60%も…」、NY観光業で深まる懸念
-

アメリカのスーパーの食材に「危険なレベル」の残留農薬、気をつけるべき野菜や果物は?
-

生ごみのコンポスト義務化、守られず ごみ分別違反に4月1日から罰金
-

トレジョの人気すぎるミニトートに新色、各店舗からは「買えた」「買えなかった」の声 ebayではすでに約16倍の価格で転売!?
-

日本の生ドーナツ専門店「I’m donut?」がついにNY上陸、場所はタイムズスクエア オープン日はいつ?
-

NYで「ソメイヨシノ」が見られる、お花見スポット5選 桜のトンネルや隠れた名所も
-

ティモシー・シャラメの「トラッシュコア」 目茶苦茶で個性的、若者を魅了
-

北米初のユニクロ「カフェ」がNYにオープン、気になるメニューや価格は?
-

物件高騰が続くNY、今が “買い時” な街とは? 「家を買うのにオススメなエリア」トップ10が発表