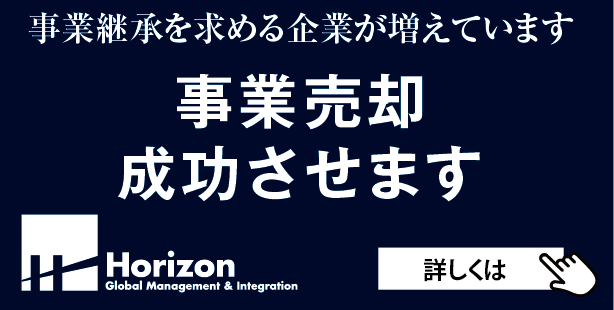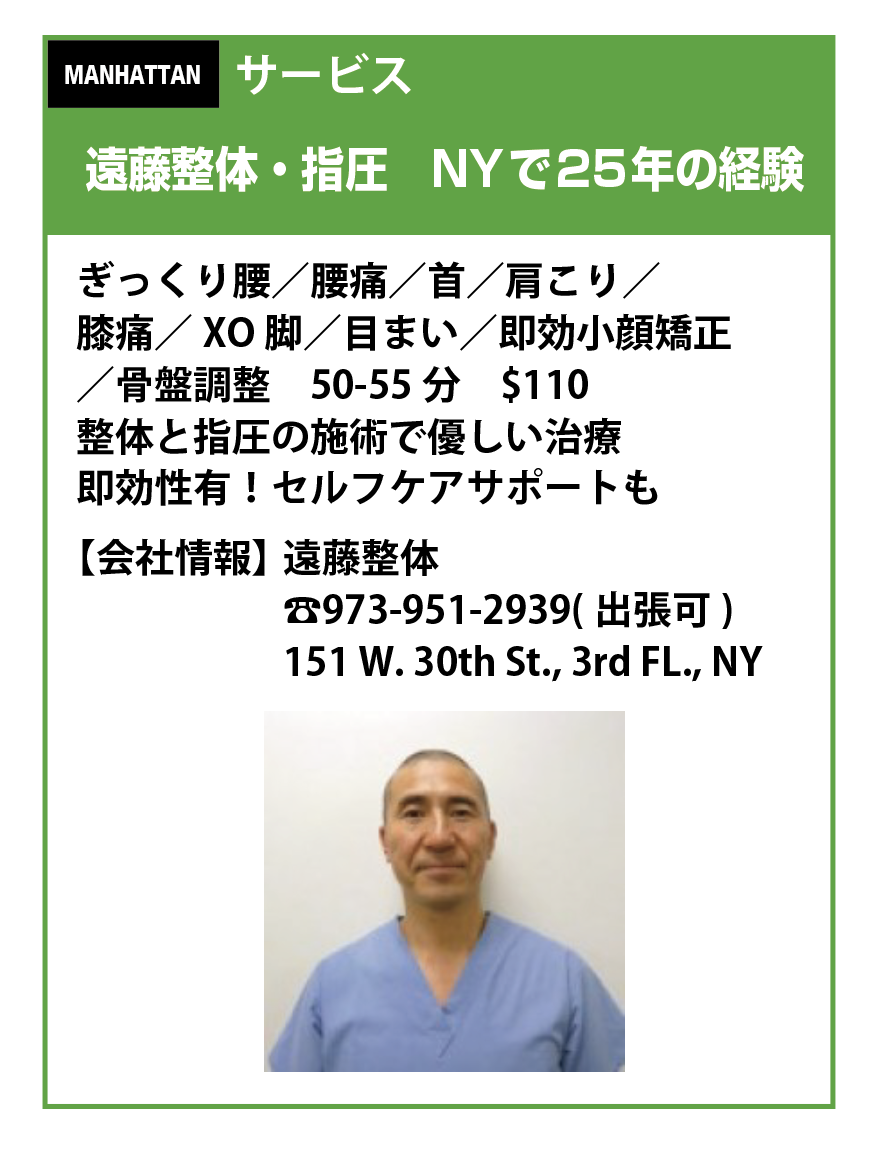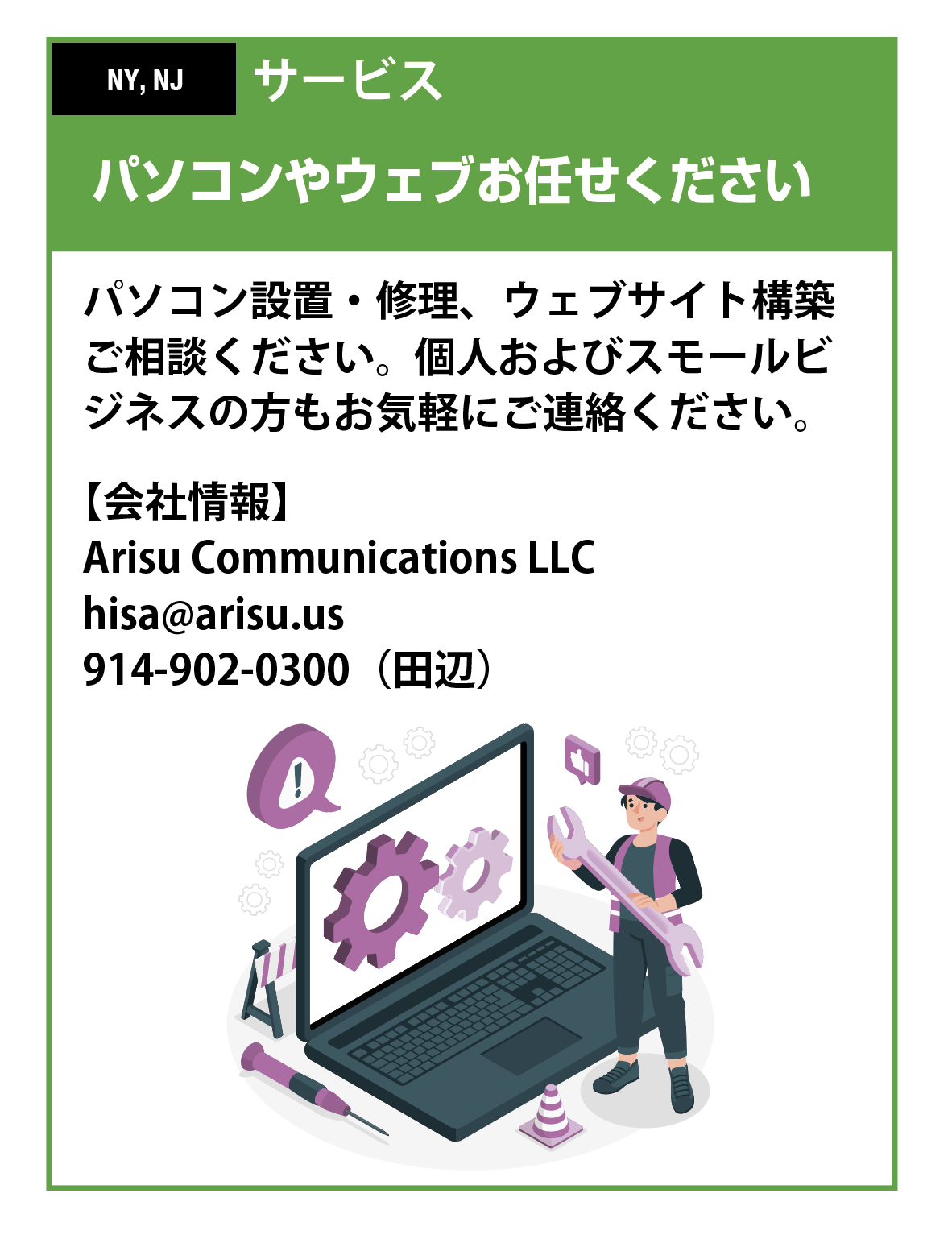あるのか初の女性大統領誕生
ニッキー・ヘイリーはトランプに勝てるのか? (中3)
(この記事の初出は2024年1月17日)
「トランプなきトランプ主義」の実行者
ヘイリーは、2016年の共和党予備選ではテッド・クルーズ上院議員(テキサス州選出、53歳)を支持した。実際、初戦のアイオワでトランプは2位となり、クルーズに敗れた。しかし、その後、トランプが次々に予備選を制し、共和党の指名を獲得すると、トランプを一切非難しなくなった。
そのためなのか、トランプはヘイリーを政権内に入れ、国際連合大使に指名した。選挙期間中に候補者を支持しなかった人物が、その候補者が大統領になったときに政権入りをするのは極めて珍しいことである。
ただ、トランプと指名を争ったクルーズも、トランプが大統領に決まると、トランプ批判を一切やめてしまった。こうして共和党はトランプに乗っ取られたかたちになってしまった。
では、ヘイリーは国連でなにをしたのだろうか?
国連をほとんど相手にしようとしないトランプの忠実な下僕となり、トランプの政策を淡々と実行した。イスラエル全面支持を打ち出し、国連がパレスチナ人の扱い方でイスラエルを非難すると猛然と抗議し、トランプの要望どおりアメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移すことを要請した。
また、核実験を続ける北朝鮮に対しては、経済制裁を続けることを支持し、同じくイランに対してもオバマ政権が取りつけた核合意を反故にすることに注力した。
こうしたことから、トランプがいなくてもトランプ政策を行う。つまり、ヘイリーは「トランプなきトランプ主義(Trapism)」の実行者とされたのである。
共和党内には、トランプの下品でオレさま性格を嫌う人間は多い。しかし、トランプの保守政策そのものには賛同している。そのため、ヘイリーはトランプと穏健保守の橋渡し役とみなされていた。
心変わりして大統領予備選出馬を決める
トランプに対してほとんど批判をしないことから、当初、ヘイリーは大統領選に出ないものと思われていた。実際、2021年4月には、「トランプ氏が出馬するなら私は2024年の大統領選に出ない」とメディアに対して述べている。
あの忌まわしい連邦議会襲撃事件に関しても、トランプが選挙結果を覆そうとしたことや議事堂襲撃に向かう群衆を扇動したことを、「投票日以来の彼の行動は歴史によって厳しく裁かれるだろう」と非難はしたが、下院がトランプを弾劾起訴すると、「トランプ氏はむしろ被害者」という認識を示した。そうして、「就任前に叩きのめし、退任後にも叩きのめすとはいいものではない。いい加減どこかで、許してあげましょうよ」と述べたのである。
しかし、ヘイリーはどこかで心変わりした。それは、トランプが合計91の罪に次々に問われ、4回も起訴されて裁判を抱えたせいかもしれない。
ヘイリーの追い上げと訴訟続きに疲れが
さすがの共和党支持者も、熱狂的なトランピスト(Trumpist:トランプ支持者)でないかぎり、刑事裁判を4つも抱えている人間を支持できないだろう。ところが、トランプの支持率は、罪状が増えるたびにアップしていったのだから、良心的な共和党支持者は頭を抱えてしまった。
トランプは昨年暮れ、コロラド州とメーン州の市民団体から「大統領選出馬資格」剥奪訴訟を起こされ、両州の最高裁がこれを認めた。ただ、トランプは連邦最高裁に上訴したため、決定は先送りされている。
おそらく、選挙期間中に連邦最高裁が決定を下すことはないと見られているので、トランプは堂々と選挙戦を続けている。
ただ、昨年は歯牙にもかけなかったヘイリーの追い上げにトランプは少々慌て出している。アイオワ入りした後の演説で、ヘイリーを「グローバリストのために政治を行う」と非難し、「私はアメリカ国民のために政治をする」と言った。
また、SNSではアイオワ入りしてデモインのホテルに入るトランプの歩き方がバランスを崩していることが注目され、「相当疲れている」「なにか医療的問題があるのでは」との声が上がった。このとき、トランプはトレードマークの赤のネクタイも着用していなかったので、そのこともSNSで話題になった。
(つづく)
この続きは2月20日(火)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで