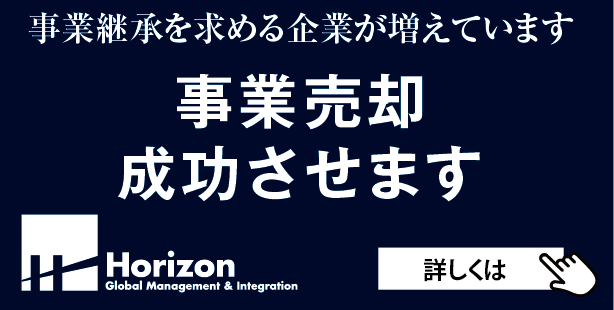(この記事の初出は2024年2月6日)
「なぜ株価は上がるか?」の説明は本当か?
一般的に株価は、景気や経済成長に連動して、上がったり下がったりするものと思われている。景気がよくて経済が成長していれば、企業業績も上がり、株価も上がるとされている。
しかし、ここ半世紀の歴史を見ると、株価は景気と経済成長をはるかに上回って上昇している。たしかに経済成長とは連動するが、その上がりかたはNYダウにしても、戦後の日本株を見ても、あまりに極端ではなかろうか。
1990年以降、日本は「失われた30年」に突入した。それはいまも続いている。したがって、株価が上がらなかったのは当然で、いま、バブル以降の最高値を更新し続けても驚くようなことではない。
ただし、なぜいまバブル期に迫る上がり方をするのかは説明がつかない。景気自体はコロナ禍を脱して上向いてきたというものの、その実体はスタグフレーションで、人々の生活は困窮し、今年の経済成長率もよくて1.0%をやや上回る(政府見通しは1.3%)程度だからだ。
ところが、現在の株価急上昇については、毎日のように専門家、アナリスト、経済メディアが、その理由をとうとうと述べている。しかし、はたしてそれは本当なのだろうか?
日米ともに「納得感」がある株価上昇理由
NY株価の上昇については、次のように説明されている。
ダウやナスダックに関しては、IT関連銘柄の大型株が牽引、最近ではメタの業績が想定外によかったからとされている。メタを含む、いわゆる「マグニフィセント・セブン」は、昨年来の上昇率が50〜200%に達している。
また、インフレであっても、雇用統計もよくて好景気だというのが米メディアの共通認識だ。さらに、FRBの利下げ時期が遠のいたことも、株価上昇のための好材料として挙げられている。
一方、日本株に関しては、円安による輸出大企業の業績が好調、外国人が日本株を割安と見て買い越していること、中国人が上海株から日本株に乗り換えていること、さらに今年から始まった「新NISA」人気が加熱していることなどが挙げられている。
なるほど、どれも「納得感」が得られる説明で、たしかにそのとおりだろう。しかし、たとえそれらの理由が正しいとしても、それだけでここまで株価は上昇していいものなのだろうか。
世界経済は成長し続けるという神話
というわけで、専門家やアナリストが、当たり前すぎて言わないことを、次に書く。
株価が上がるのは、「買いたい人間が売りたい人間より多いから」の一言に尽きる。これは、株に限らず、モノ、サービスみな同じである。
そもそも株価は会社が発行するものだから、発行数が限られている。よって、それが常に不足する状況がつくられ、買いたい人間がいれば株価は上がり続ける。
この状況をつくっているのが、メディアや専門家、アナリスト、そして政府であり、彼らは、世界経済が常に成長していくことを前提にものを考え、情報を発信している。
産業革命以後、世界経済は成長・膨張し、世界のGDPは何十倍、何百倍にもなった。だから、今後も成長していくのは間違いないというのだ。
その結果、いまや誰もが世界経済全体に投資していけば、必ず資金は増えるというのである。この理屈により、日本では新NISAにより「S&P500」「オルカン」(オールカントリー)などへのインデックス投資がヒートアップした。
しかし、世界経済が成長を続けるということも、それにより株価が上がり続けるということも、非科学的なオカルト、ただの神話にすぎない。
仮に、世界経済の経済成長率を年率4%としてみると、100年後に世界のGDPは現在の49倍に、300年後には約12万9000倍になる。もっと低い2%と仮定しても、100年後に現在の7倍に、300年後には370倍になる。これはどう考えてもありえない。
なぜなら、私たちは、地球という限りある「有限世界」に住んでいるからだ。無限成長などありえないのである。人類史を見れば、経済成長をしなかった年などいくらでもある。
(つづく)
この続きは3月5日(火)発行の本紙(メルマガ・アプリ・ウェブサイト)に掲載します。
※本コラムは山田順の同名メールマガジンから本人の了承を得て転載しています。

山田順
ジャーナリスト・作家
1952年、神奈川県横浜市生まれ。
立教大学文学部卒業後、1976年光文社入社。「女性自身」編集部、「カッパブックス」編集部を経て、2002年「光文社ペーパーバックス」を創刊し編集長を務める。2010年からフリーランス。現在、作家、ジャーナリストとして取材・執筆活動をしながら、紙書籍と電子書籍の双方をプロデュース中。主な著書に「TBSザ・検証」(1996)、「出版大崩壊」(2011)、「資産フライト」(2011)、「中国の夢は100年たっても実現しない」(2014)、「円安亡国」(2015)など。近著に「米中冷戦 中国必敗の結末」(2019)。
RECOMMENDED
-

アメリカのスーパーの食材に「危険なレベル」の残留農薬、気をつけるべき野菜や果物は?
-

生ごみのコンポスト義務化、守られず ごみ分別違反に4月1日から罰金
-

なぜ? アメリカの観光客が減少傾向に「30〜60%も…」、NY観光業で深まる懸念
-

北米初のユニクロ「カフェ」がNYにオープン、気になるメニューや価格は?
-

NYで「ソメイヨシノ」が見られる、お花見スポット5選 桜のトンネルや隠れた名所も
-

実は面白い “トレジョ” のアート、ディスプレイからパッケージまで「気が付かないのはもったいない」
-

物件高騰が続くNY、今が “買い時” な街とは? 「家を買うのにオススメなエリア」トップ10が発表
-

NYのクイーンズに巨大な「エンタメ施設」が誕生、フードホールにライブ会場も 総工費は約80億ドル
-

コロンビア大のブランド「色あせる」 御難続きで、合格者が敬遠
-

NYの水道水にまさかの事実 塩分濃度が3倍に、向こう30年で許容量を超える懸念