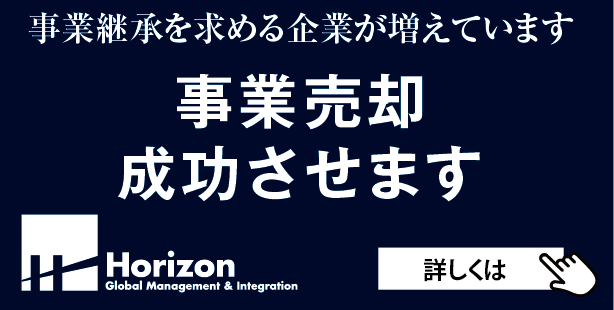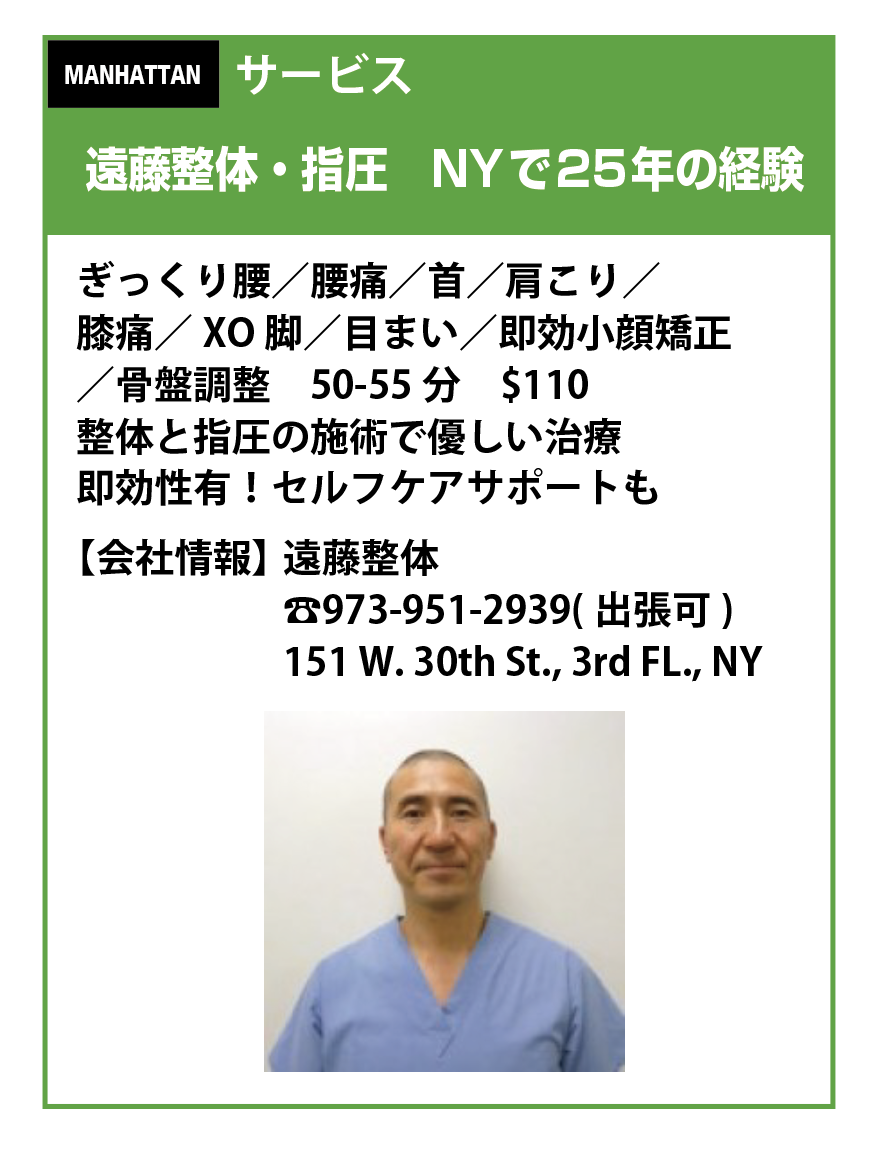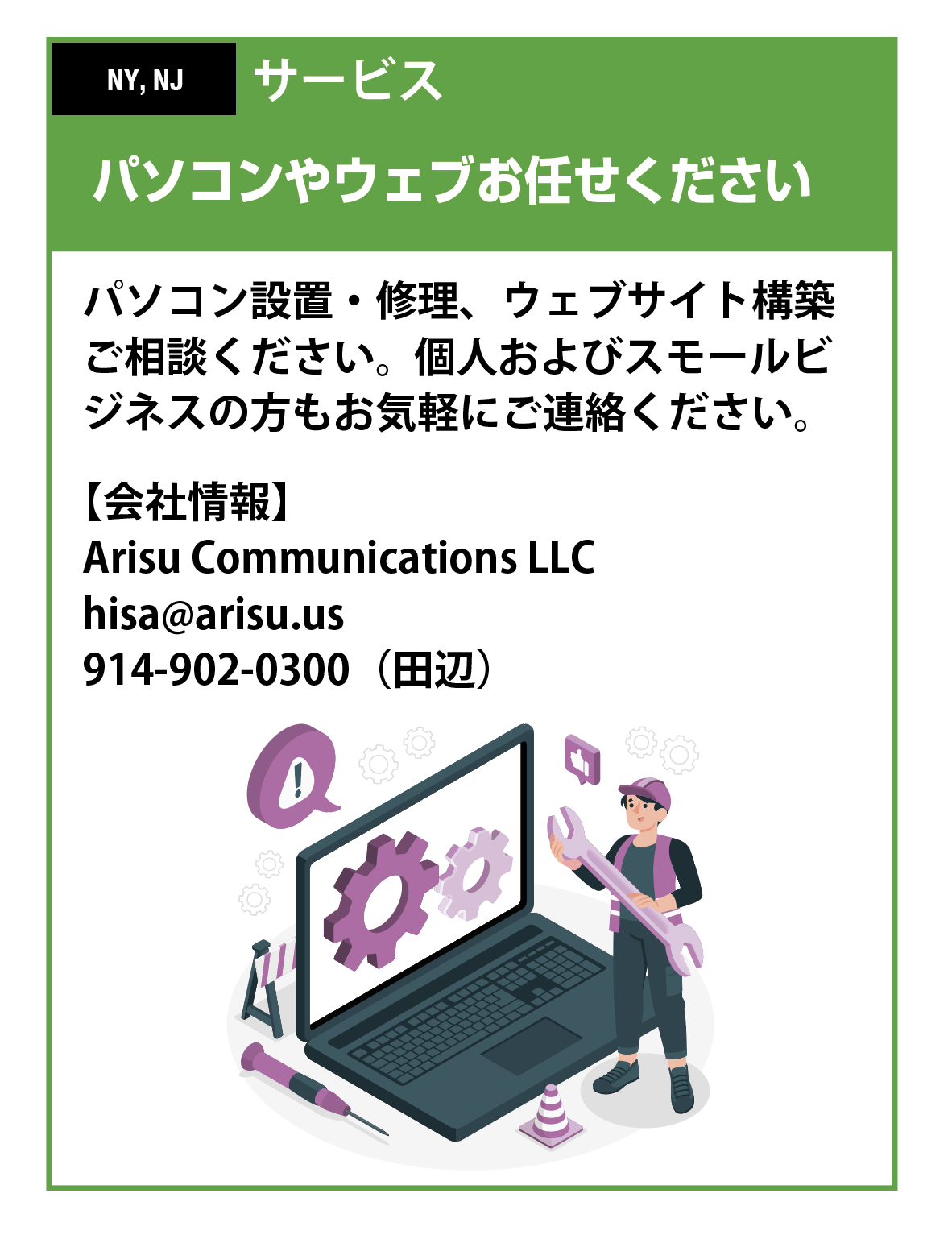アートのパワー 第39回 『J. T. Sata: Immigrant Modernist(J.T.サタ:移民のモダニスト)』(上)(ロサンゼルス全米日系人博物館 Japanese American National Museum, LAにて9月1日まで)


ゼラチン・シルバープリント。全米日系博物館、
フレンク、マリアン佐多夫妻と家族より寄贈。(2005.187.2)
ロスにある全米日系博物館(JANMジャノム)で『J. T. Sata: Immigrant Modernist(J.T.サタ:移民のモダニスト)』展が開催されている。同作家初の個展で、展示写真は60枚。佐多忠直(日系1世 、1896-1975)は、1918年、22歳の時にアメリカに移住した。ジェームズという英語名をファーストネームにし、作品には J.T. Sata と署名した。
20世紀前後に移民した若い男性のほとんどが農家出身の次男坊や三男坊だったが、サタは武士の血統だった。佐多家は薩摩藩の家臣団の家格で3番目の一所持(30家、私領主)で、明治維新まで22世代続いた家系だった。サタは生涯、自分は1896年鹿児島で生まれたと信じていた。維新後、武士階級が廃止され生活のために北海道開拓に向った元士族もいた。父親はそこで忠直が生まれる前に病死した。母親のキノは亡夫の先妻の子供3人と自分の子供2人を連れて鹿児島に戻ったが、岩手出身の未亡人には鹿児島は居づらく、亡夫の妹が住んでいた沖縄に頼って行った。妹の夫が首里の市長、首里区立女子工芸学校をabandoned 首里城中に創立、理事を務めていた。キノは同校で裁縫を教えながら家族を養った。サタの息子、フランクによると、「子供の時に学んだ彼女(キノ)の価値観が、どんな外的状況にもかかわらず常に前進する強い信条、息の長い集中力、そして揺るぎない精神力を与えた」。キノは1918年に亡くなり、同年に忠直は横浜から蒸気船天洋丸でサンフランシスコに渡り、ロスに向かった(展示会カタログより)。
サタは、日本からの他の移民男性と同様に、使用人や青果市場の仕事に就いたが、画家になることが夢だった。日本を出る前に鹿児島を描いたスケッチブックを故郷の思い出に持ってきていた。しかし、そんな彼の関心を引いたのは、1921年に購入したパーマー・フォトプレイ・コーポレーションPalmer Photoplay Corporationの写真教材だった。もしかしたらサタは当時知られていた写真家H. K. シゲタの教室で学んだのかも知れない。1923年、リトル東京にアート写真を撮影する芸術写真家のグループが集まり始めた。サタは、当時最も良く知られていたロスを中心に活動したカリフォルニア日本カメラ・ピクトリアリストJapanese Camera Pictorialists of California (JCPC) の創立メンバーの一人だった。羅府新報(Rafu Shimpo)が毎年写真展を後援した他、T. イワタ美術店(カメラ、フィルムの現像、写真印刷)が1925年から毎年写真コンクールを行い応援した。何人かのメンバーはプロの写真家としてスタジオを構えていたが、サタも含めてほとんどは熱心なアマチュアだったという。

油彩、アーカンサス州ジェローム強制収容所。
写真、絵画のどちらにおいても、サタのドラマチックな
プロポーション(比率、均整)が見られる。
2016年JANMで開催された『Making Waves – Japanese American Photography 1920-1940(波を起こす:日系アメリカ人の写真、1920‐1940年)』展で、「アメリカで制作された最も先進的なアート写真のいくつかは、1920年代から1930年代にかけてロサンゼルスのリトル東京地区で日本人移民によって制作された。彼らの写真は、アメリカの太平洋岸で活動する他の日系アメリカ人によるプリントとともに、出版され、国際的に展示され、高い評価を受けた。しかし、第二次世界大戦勃発時の恥ずべき日系アメリカ人強制移住の際に、彼らの写真のほとんどが紛失・焼失してしまった」と本展を企画したデニス・リードは語っている(デニス・リードはコレクター、アジア系アメリカ人写真の第一人者で、ロサンゼルス・バレー・カレッジの名誉教授)。彼らの作品はエドワード・ウェストンやラズロ・モホリ=ナジに賞賛された。
エドワード・ウェストンをリトル東京の日本人写真家に会わせたのは、日本的なものに興味を持っていた写真家のマーガレ・メイザーだった。ウェストンはリトル東京で少なくとも3回展示会を行った。興味深いことに、エドワード・ウェストンの有名な写真のひとつ、半分に切られたアーティチョークの写真は1930年に撮影されたもので、サタは同じ被写体を1927年に撮影している。この頃、ウェストンはモダニストに傾倒しつつあった。
この続きは8月9日(金)発行の本紙(メルマガ・ウェブサイト)に掲載します。
アートのパワーの全連載はこちらでお読みいただけます

文/ 中里 スミ(なかざと・すみ)
アクセアサリー・アーティト。アメリカ生活50年、マンハッタン在住歴37年。東京生まれ、ウェストチェスター育ち。カーネギ・メロン大学美術部入学、英文学部卒業、ピッツバーグ大学大学院東洋学部。 業界を問わず同時通訳と翻訳。現代美術に強い関心をもつ。2012年ビーズ・アクセサリー・スタジオ、TOPPI(突飛)NYCを創立。人類とビーズの歴史は絵画よりも遥かに長い。素材、技術、文化、貿易等によって変化して来たビーズの表現の可能性に注目。ビーズ・アクセサリーの作品を独自の文法と語彙をもつ視覚的言語と思い制作している。
RECOMMENDED
-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由
-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証
-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?
-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック
-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気
-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ
-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?
-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング
-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?
-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで